
東京科学大学(Science Tokyo)の田中雄二郎学長と5人の学生が、学び、研究、キャリア、そして大学への期待について語り合いました。専門も学年も異なる学生たちの声から、「これからの大学のかたち」が見えてきます。日頃から学生たちと接している3人の教員も参加しました。
大学──それは異なる専門と多様な価値観が出会い融合する場所
田中学長 今日はお集まりいただきありがとうございます。まずは自己紹介をお願いします。

桐林 材料系博士後期課程2年の桐林龍寿です。抗菌・抗ウイルスのセラミックス材料を研究しています。趣味はレコードや骨董品の収集、化石採集などです。「時間を超えて残るもの」に惹かれています。中東情勢や資源問題、感染症など、世界の構造にも目を向け、研究に活かしたいと考えています。

小泉 情報通信系修士1年の小泉香奈です。人とAIの協調が社会に与える影響に関心があります。ドローンのアクセスポイント最適化を研究中で、「使う側」から「創る側」への視点が今の原動力です。メークや色彩にも興味があり、技術と人のつながりを大切にしたいです。
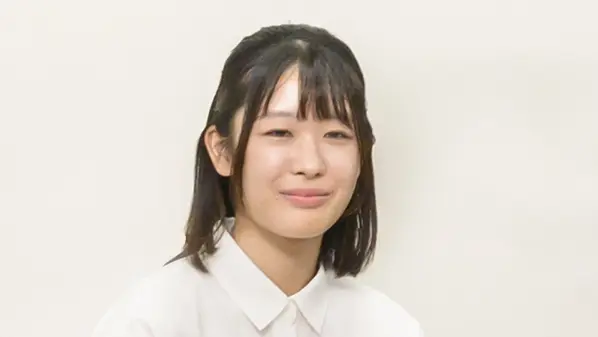
ヘイムス 医学科3年のヘイムス・エレイナ・ユウカです。救急医療サークルTESSOやHSLPというリーダー育成カリキュラムに参加しています。AIと医療の接点に強い関心があります。技術そのものより、それが人にどう届くかを重視しています。映画や読書、ランニングで気分転換しながら、視野を広げています。

林 歯学科3年の林大翔です。口腔外科や病理に興味があり、原因や病態を深く理解し、治療だけでなく予防や教育にも貢献したいです。高校時代から「なぜそうなるのか」という構造的な理解に興味があり、医学的視点が求められる口腔分野に魅力を感じています。弓道部や軽音楽部で活動中です。
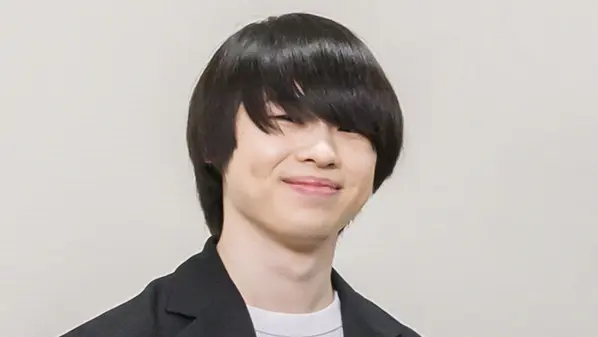
中村 医学科1年の中村瑠那です。華道、フットサル、陸上競技、子どもたちに対するボランティアに取り組むCCC、アジア医学生連絡協議会AMSAなど幅広く課外活動に取り組んでいます。交流を通じて自分を知るのが好きです。倫理的・法的・社会的課題を意味するELSIや科学技術社会論STSなど、科学技術と社会の関係にも関心があります。倫理の視点は、医学にも重要だと考えています。

「立志プロジェクト」が育む対話の力
田中学長 大学が統合されてから、何か変化や気づきはありましたか?
桐林 まだ完全に統合された段階ではないと思うので、大きな違いは実感できていないですね。ただ、自分の研究は、抗菌・抗ウイルスという医学の分野とセラミックスという材料の分野が融合したところなのですが、医学系の研究室は旧東工大にはありませんでした。そうした二つにまたがるような分野の共同研究をやりやすい環境が、今後整っていきそうだという期待感があります。
中村 私は1年生なので統合前は知りませんが、週1回月曜日に大岡山の「立志プロジェクト」で理工学系の学生と一緒に学ぶことは、学びの面からも、人と人とのつながりという面からも、とても有意義な時間でした。立志プロジェクトでは、科学倫理全般やELSI、ダイバーシティ&インクルージョンについて理工学系と医歯学系がともに学びました。私は、同じ問題に関して理工学系の人たちは結構視点が違うと感じて、理工学系の人たちが一般的に何を考えているのかを知ることができ、とても勉強になりました。また、私自身の考えを彼らにどう伝えるか、医歯学系に詳しくない人にどうやったら理解してもらえるのかということを考えながら発表したので、自分自身を見つめ直す機会でもあったと思います。
田中学長 視点が違うというと?
中村 例えば、水俣病についての講義があったのですが、理工学系の人は当時の時代背景を考えると水俣病はある意味やむを得なかったと考える一方、私たち医歯学系は地元住民の感情に目を向けてそこを深堀りして考えるという傾向があって、違いが顕著に出ました。
田中学長 理工学系の学生からすると、数十年前の基準だとそれは仕方がない、今の基準で裁いてはいけないということ?
中村 はい。その時代の科学者にそこまでの配慮を求めるのは間違っているし、今それを批判するのは違うと。
田中学長 なるほど。医歯学系の学生は、水俣湾に死んだ魚が大量に浮いているのに見過ごすのはおかしいという感じかな。それは、理工学系、医歯学系ではっきり分かれた?
中村 はっきりではありませんが、そういう傾向がありました。
田中学長 小泉さんはどう?
小泉 私の場合、立志プロジェクトはもう数年前で、実際にグループでどのような意見があったか明確に憶えているわけではありませんが、ディスカッションの中で「当時はおそらく基準の違いもあり仕方ない側面もある」といった感じの話になっていた印象があります。
田中学長 小泉さんの時代は理工学系の学生しかいないでしょう? 毎年水俣病のテーマでやっているの?
岡田先生 旧東工大の時から大切にしているテーマで、継続的にやっています。

田中学長 なるほど。小泉さんのように理工学系の学生のみの場合は、当時のことを今の基準で裁くのはおかしいという意見がほとんど?
小泉 裁くのはおかしいというより、同じようなことを繰り返さないように、批判ではなく教訓にしていこうという意見が強かったと思います。
田中学長 桐林くんはどうでしたか?
桐林 自分のときは、水俣病の講義を聴いた上でディスカッションしました。その講義で理工学系の先生は「水俣病は企業だけの問題ではない」というような見解を出していた。その後のディスカッションでは、自分のグループは、その企業に対する批判的な意見が多かったです。
田中学長 私の出身高校の集まりがあって、旧医科歯科大に現役で入った2年生に混ざって1浪してScience Tokyoに入った1年生がいました。彼が言っていたのは、自分は1年遅れて入ったので立志プロジェクトで大岡山に行くことになり、そのとき総合大学に入ったんだとしみじみ感じたと。1浪して良かったとは言わないけれども、全く違う考え方の人たちと一緒になって議論することができたのは大きいと言っていました。
教員から見るScience Tokyoの「立志プロジェクト」、今後の展望
田中学長 教員から見て大学統合後の立志プロジェクトは以前と違いますか。
岡田先生 クラスの雰囲気が全く違いますね。理工学系のみのときは、良くも悪くも全員が同質であるという前提で話が進んでいました。科学者や技術者になる人たちが、みんなで水俣病の話を受け止める、というふうな、科学者や技術者が悪いことをした、自分たちが責められている、というスタンスで話を聞いていました。しかし、医歯学系の学生も含めて一緒に聞くと、被害者と加害者という単純な位置づけでなく、例えば医療者の中にも患者に寄り添い原因究明に尽力した人もいれば究明に消極的だった人もいたわけで、もっと大きな視点で問題の構造を捉えることになります。自分たちがもしその場にいたらどうすればよかったんだろうかという形で、責められる一方ではない聞き方ができ、それをまた立場の違う人たちで意見をぶつけ合って考えを深めることができる。議論の仕方がこれまでと全く違っていたというのが印象的でした。
田中学長 猪熊先生はいかがですか。理工学系の学生が目の前に現れてどうですか。
猪熊先生 そうですね。医歯学系ではもともと「グローバル教養総合講座」という授業があり、その最終回では少人数グループ発表を行っていました。これは旧東工大の「立志プロジェクト」にはなかった要素でしたが、Science Tokyoの「立志プロジェクト」では、理工学系と医歯学系がなるべく混ざった少人数グループをつくり、最終回でグループ発表してもらう形をとり入れました。印象的だったのは、看護の学生が「水俣病は公害というけれど、公害というのを英訳しようにもぴったりの言葉がない。人は名前が付いて初めて病気を認識し、問題を捉えることができる。けれどむしろ名前が付くまでがとても苦しい。名前がないと自分の苦しみを言葉にして説明することができないから。水俣病も認定されるまで苦しかった人たちがたくさんいて、名前が付いて初めてそれが分かったんだと思う」という発表をしたんです。これに対して理工学系の学生は、「病気に名前が付く瞬間というのを初めて自分として腑に落ちて理解した」「何かをつくるときに、その技術に名前があるかないかなんて考えたことがなかったけれど、新しくつくるということは名前を付けていくことと同じで、名前があって初めて人に説明することができる」と話していました。医歯学系の学生たちだけで話をしているときには医療者という立場のみでしたが、今回の立志プロジェクトで、理工学と医歯学の間に橋が架かって、学生たちが各々相手の領域に渡っていくという瞬間を見せてもらい、とても良かったと思います。

林 私たちは先ほど猪熊先生がおっしゃった「グローバル教養総合講座」を医歯学系の学生だけでやっていましたが、医療者側であるというバイアスがかかっていると思う場面が非常に多かった。いろいろな視点を取り入れられるようになったのは、少しうらやましい部分ですね。
ヘイムス 私も同じ意見で、医療の中で医学部だけの視点に依ってしまうという現象があります。大学では「多職種連携」といった授業もあるのですが、さらにこうした授業があるともっと視点が増えるという点で、うらやましいと思いました。
田中学長 山口先生、1年生だけがこういうことができるというと、2年生以上がかわいそうじゃない?
山口先生 今、さまざまな先生方と何らかの形で2年生以上の学生が大岡山キャンパスで学ぶ機会を創出しようと相談を始めています。

田中学長 理工学系の大学院は複合系があるでしょう?
桐林 そうですね。
田中学長 そこに医歯学は入ってこない?
桐林 まだないですね。
田中学長 せっかく統合したんだから何かあるといいよね。大学統合は海外でもあるけれど、先行事例を見ると学生が先頭に立ってなじんでいくとだいたい統合がうまく進むといわれている。視点が全然違うという話があったけれど、なぜだろう。どちらも同じ理科系でしょ。
山口先生 大学に入ってすぐに行われた授業の時点で、もう既に視点が違っているのが面白いですよね。まだ医歯学系や理工学系の思考が入っているはずはないのに。逆に学年を経るごとに学生も成長して視点も変わるし、まったく同じ教材で、2年生、3年生、4年生でやってみるプロジェクトもいいですね。
多彩な学生が描く科学と社会の可能性
田中学長 皆さん深く考えていて、学長として誇りに思います。大学へのイメージと期待について聞かせてください。
中村 本学には「科学の最前線を切り拓く使命感」があります。今は専門の学びに加え、人とのつながりを大切に、さまざまな価値観に触れたいです。AIや生体工学が医療にもたらす可能性にも関心があります。
林 本学は「大学の赤ちゃん」。統合で生まれた新しい大学として、成長を見守りたいです。旧東工大の学生との交流を通じて統合を実感したい。歯科医療と理工学の融合にも期待しています。
ヘイムス 本学は「未来を設計するフロントランナー」。社会への貢献を見据えた姿勢に共感しています。実践的な学びの場がもっと増えるとうれしいです。医工連携サークルの立ち上げにも関わっています。
小泉 「次世代を切り拓く大学」と感じています。学びを社会実装へとつなげることに関心があり、グループワーク型の講義で課題解決に取り組んだ経験が大きな学びになりました。
桐林 「科学教育の老舗百貨店」という印象を持っています。分野を超えた知が集い、多様性と専門性が共存している。現在は抗菌・抗ウイルス性セラミックスの研究に打ち込んでおり、理論と応用の両立を意識しています。
「知の百貨店」から「開かれた学び」へ―大学の未来構想

ヘイムス 学長には、今から5年後、10年後の大学がどのようになっているか、というビジョンはありますか。
田中学長 私の仕事は方向付けだと思っています。土壌をつくるということ。そこにどんな種をまき、それがどう育ち、どんな花を咲かせるかというのは、みなさん学生や教員たちの作業です。理工学系と医歯学系を1つの大学にまとめましたが、大岡山や湯島といったキャンパスを越えた有機的な交わりが生まれるようなフレームワークを5年のうちにはつくりたい。そのあとどうなるかは、あなたたち次第です。
ヘイムス 他の大学と違って何か新しくできるようになるのか、例えばもっと学生が自由に交流できるフレームワークや環境づくりを具体的にお考えですか。
田中学長
クラブ活動などはもっと一緒にやったらいいと思います。2028年からは理工学系、医歯学系合わせて1,300人の1年生すべての授業を一緒にできたらと思っています。もっとネットワークが広がるはずです。
理工学系はどうしても未来を志向しますよね。「ありたい未来」という言葉が象徴するように。これに対して医歯学系は目の前に患者さんがいるので、目の前を見る傾向がある。だからこそ見る視点が違うわけで、医歯学系が明日の医療はどうなるか考えていいはずだし、理工学系が今の社会は何を求めているんだろうと考えてみることも大事だと思います。その両方があると良い理工学者や医療人が生まれると期待できるし、その交わるところに新しいものが生まれると思うのです。
私は肝臓の研究をしていましたが、本当に狭い領域で研究していたんですよ。レッドオーシャンとはこういうことを言うんだというくらい。でも、理工学系と医歯学系が交わると新しい可能性が出てきて、エメラルドグリーンのブルーオーシャンになる感じがする。そこでやる研究は楽しいし、やりがいもあるだろうし。
「学び続ける大学」のビジョン―卒業後にも開かれた知の場を
田中学長 今年、四大学未来共創連合の新しいパートナーとしてお茶の水女子大学が加わりました。全体で見るとジェンダーバランスが一気に上がるし、新しい文化も加わるということで、新しい大学連合ではキャンパスを巡るようなスクーリングをやったらどうかという構想があります。ジェンダー以外にも、東京外国語大学は外国人比率が40%だそうで、国際共修を体験できるじゃないですか。他にも一橋大学のキャンパスは中世の大学みたいな感じだし、大岡山はロボットみたいな建物が迎えてくれて、湯島に来れば病院が見られる。お互いのキャンパスの魅力を感じて、そこで普段と違う人たちと議論できたら、かなり視野が広がると思うんですよね。
中村 私は今、教養課程で学んでいるところですが、将来の科学者や医療者が専門外の教養を学んだり、他分野の知識を得て視野を広げることは、とてもいい経験になると思っています。
田中学長 社会の中で科学者や医療者だけで生きていくことはあり得ないですからね、さまざまな人たちと関わる中で生きていくためには、物事について共感できるような共通言語があったほうがいい。日本国内はもちろん世界でも同じで、それが教養というものですよね。時代を超えて、世代を超えて共有できるものは数多くあって、そういうものを身に付けることも大事ではないかと思います。
座談会を終えて
写真左から順に、各参加者のプロフィールと感想を紹介します。

岡田 佐織(おかだ さおり)
東京科学大学リベラルアーツ研究教育院 准教授
立志プロジェクトで水俣病について話し合ったことが印象に残っていると聞き、嬉しく思いました。これからも、さまざまな人と出会い対話しながら、専門を極めつつ専門の外へと学びを広げていってほしいです。
林 大翔(はやし ひろと)
歯学部歯学科学士課程3年
学年や専門を超えて会話できたのが新鮮で、これこそ大学のあるべき姿だと思いました。
小泉 香奈(こいずみ かな)
工学院情報通信系情報通信コース修士課程1年
課題解決に必要なのは多様な視点だと再確認できました。実社会にもつながる議論でした。
中村 瑠那(なかむら るな)
医学部医学科学士課程1年
理工の方と学び合う中で、自分の意見を磨く機会を得ました。とても刺激的でした。
田中 雄二郎(たなか ゆうじろう)
東京科学大学学長
本日の座談会は、「学びの力は、人と人の対話から生まれる」ことを改めて感じさせてくれる時間でした。皆さんの声を、これからの大学づくりにしっかりと生かしていきます。
ヘイムス・エレイナ・ユウカ
医学部医学科学士課程3年
自分の関心を新たに確認できただけでなく、他分野への尊敬も深まりました。
桐林 龍寿(きりばやし りゅうじゅ)
物質理工学院材料系材料コース博士後期課程2年
自分の研究の意義を見つめ直すきっかけになりました。もっとつながっていきたいですね。
猪熊 恵子(いのくま けいこ)
東京科学大学リベラルアーツ研究教育院 教授
学生の皆さんが専門や年齢の違いを超えて、目の前の相手の話に真摯に耳を傾ける姿勢がとても印象的でした。若く柔軟な受容力と包容力をそのままに、今後も多様な仲間との実り多き交流を続けてほしいと願っています。
山口 久美子(やまぐち くみこ)
東京科学大学ヘルスケア教育機構 医歯学教育開発室 准教授
同じテーマの議論を経験した、「元・大学一年生」が、年代を超えて自らの学生時代の経験を共有する場面に感動しました。多様な仲間との対話を通じてさまざまな視点があることを経験し、学びを深めることに期待します。
所蔵品説明
本ページに掲載されている写真は東京科学大学図書館御茶ノ水図書館の所蔵品を用いております。
- [所蔵品]
- 解体新書(初版本):杉田玄白・前野良沢らが翻訳し、1774年に刊行した日本初の本格的医学書。西洋解剖学を伝える貴重な一冊。
関連リンク
統合報告書2025
財務情報に加え、社会貢献やガバナンス、非財務情報を統合して、ステークホルダーの皆様にご報告するものです。
本学の教育・研究、社会に対する取り組み、経営戦略などをご報告し、さらなる飛躍に向けた道筋を示します。
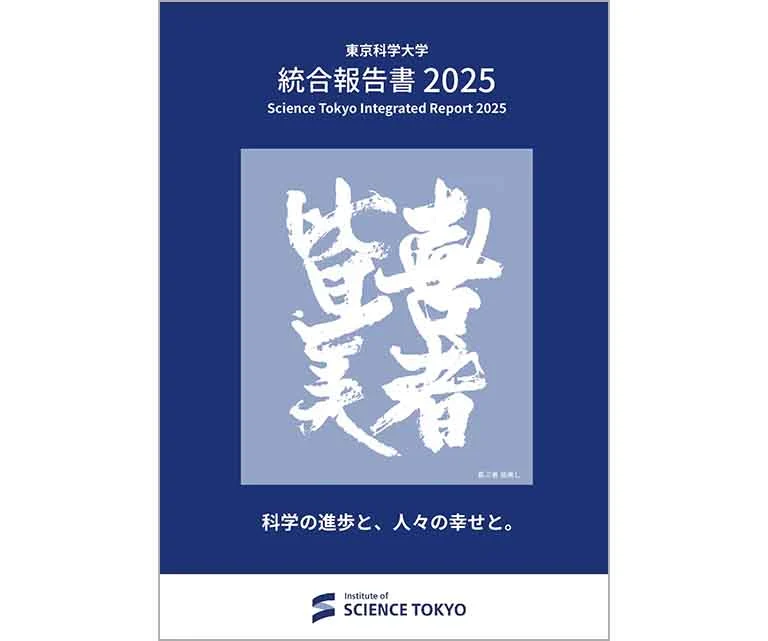
取材日:2025年7月3日/湯島キャンパスにて