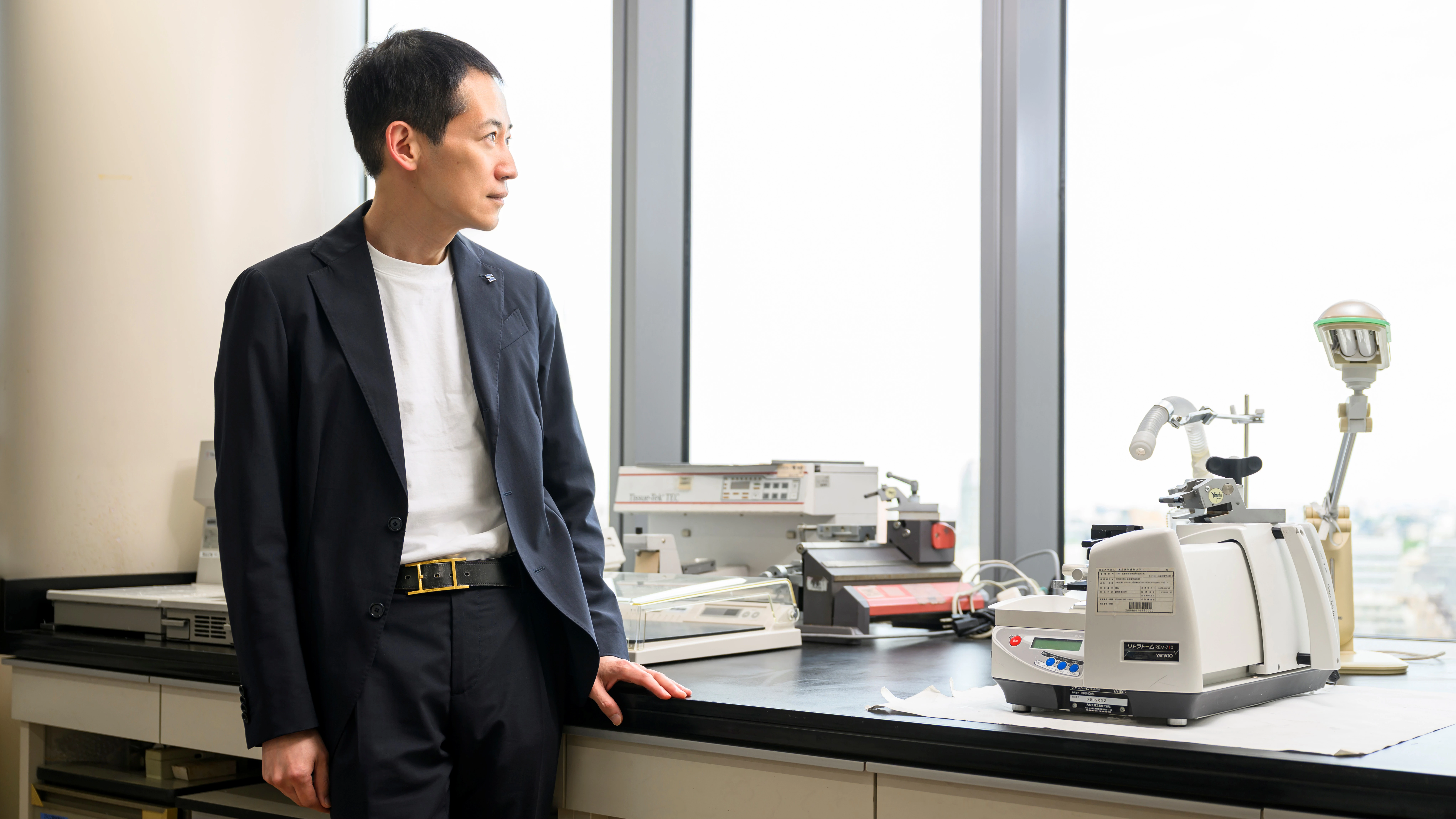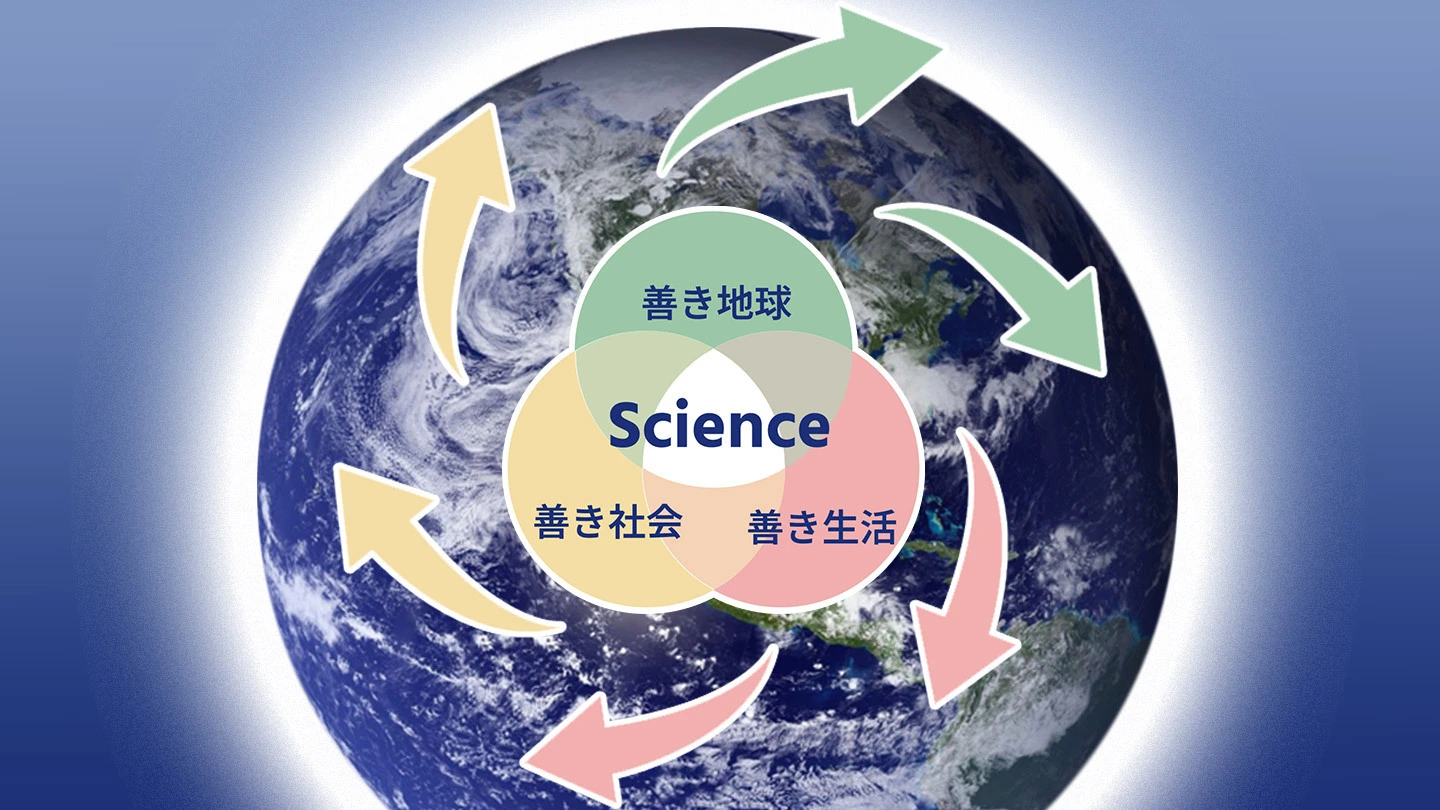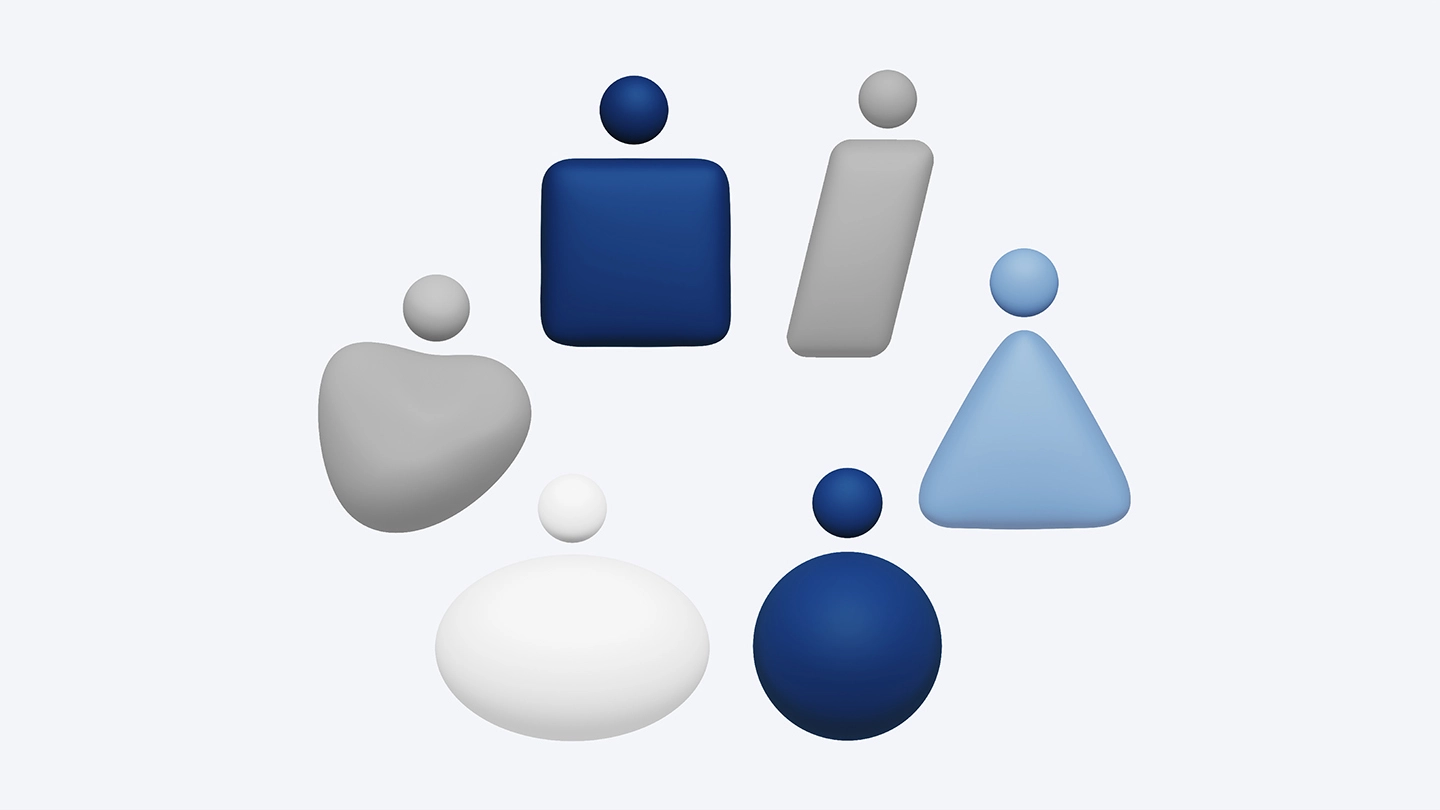東京科学大学(Science Tokyo)理工学系の同窓会である一般社団法人蔵前工業会は、10月18日に「第50回蔵前科学技術セミナー 科学で善き未来を拓く~善き生活、善き社会、善き地球を目指して~」を開催しました。会場の蔵前会館くらまえホールおよびオンラインには、卒業生を中心に、一般の方、学生、教職員を含めて約250人が参加しました。

セミナーには、Science Tokyoのビジョン駆動型・融合研究体制「Visionary Initiatives(VI)」のプログラム・ディレクターが登壇し、各プログラム・ディレクターが率いるVIのもとで進める研究を紹介しました。
VIは、ビジョンに共感する研究者、企業や団体、個人が参加し、共に未来社会を形づくるエコシステムを築いていく仕組みです。各プログラム・ディレクターは、Science Tokyoの取り組みと、共創によって進化する研究の姿を熱く語りました。
開会のあいさつとScience Tokyoが描く未来
開会にあたり、蔵前工業会の井戸清人理事長があいさつし、1906年の設立以来、日本の科学技術の発展を支えてきた当会の歩みを紹介しました。今回でセミナーが第50回を迎えたことに触れ、「この節目に、善き未来についてお話を伺えることを大変うれしく思います」と締めくくりました。
続いて、Science Tokyoの大竹尚登理事長が登壇。「異なる文化や価値観が出会い、融合することで新しい研究が生まれる」と、統合の意義を語りました。さらに、ビジョンを中心に、社会の一員としてエコシステムを築くことが新しい大学の姿であり、VIとは「社会とともにビジョンを実現するための機能であり、場である」と位置づけました。
開かれた共創の場をめざして
波多野睦子 理事・副学長(研究・産学官連携担当)
最初の講演者である波多野睦子理事・副学長(研究・産学官連携担当)は、「ビジョナリーイニシアティブで善き未来を共創する」と題して、VIの全体像を詳しく説明しました。
VIは、掲げた未来像の実現に向け、分野の垣根を越えて協働する新しい研究体制です。波多野理事は、こうした共創を持続的に広げていくためには、研究者に限らず、産業界や自治体、個人など、さまざまな立場の人々が対等に関われる新たな仕組みが必要だと語りました。
また、医工連携や環境技術などの事例を挙げながら、「基礎研究から社会実装までをシームレスにつなぎ、研究の成果を社会に還元していくことこそが未来の大学の使命」と語り、共創による新たな研究の形を示しました。

健康であり続けることこそ豊かさ
石川文彦 医歯学総合研究科 教授
医歯学総合研究科の石川文彦教授は、自身が率いるVI:Total Health Design 「科学はすべての人の健康と福祉のために」のビジョンのもと、基礎研究と臨床研究を橋渡しする医工連携の最前線を語りました。講演では、AIやデータサイエンスを活用した疾病予測モデルの開発、口腔環境と全身の健康を結びつける研究など、私たちの日常生活に直結するテーマが次々と紹介されました。
白血病を専門とする石川教授はさらに、理工学系研究者との連携にも触れ、ナノマシン技術やRNA工学を組み合わせ、薬を骨の特定部位に届ける新たな治療法の開発を目指していることを語りました。
石川教授は講演の中で、「cross(超える)」という言葉を繰り返し強調しながら、専門分野、世代、国境を超えて協働することの重要性を訴えました。そして、「健康であり続けることこそが真に豊かな生活、未来の基盤です。若い世代が世界に目を向け、ともに人々の健康を支えていくことが私たちのビジョンです」と結びました。

「楽しく老いる」未来へ、心と体をつなぐ共創の科学
廣田順二 副理事(医療工学担当)・副学⾧
廣田順二副理事(医療工学担当)・副学⾧は、VI:Well-Vitality Science「各人が精神的に豊かな人生を実現する」のプログラム・ディレクターを務める生命理工学院の黒田公美教授(海外出張のため欠席)に代わって登壇し、心と体の豊かさを追求する研究を紹介しました。
Well-Vitality Scienceでは、「楽しく老いる生涯」「心の豊かさと多様な生き方の実現」などをテーマに、心理学、脳科学、スポーツ医学、社会科学など多様な分野の研究者が連携して研究を進めています。
黒田教授が主導する研究では、マウスの子育て行動解析から発見された「輸送反応」をもとに、子どもの行動制御に関わる脳の仕組みを明らかにし、赤ちゃんの心拍や動きを検知するセンサ開発へと発展させています。廣田副理事・副学長は、こうした成果が睡眠障害や発達障害の早期発見などにつながることが期待されていると説明しました。
さらに、建築と医療の連携による「健康に暮らせる住環境」研究や、脳科学と法学を組み合わせた行動解析など、分野を超えた共創の広がりにも触れました。オートファジーなど老化のメカニズムを探る基礎研究にも力を入れており、「すべての人が楽しく生きる社会」を支える科学の可能性を示しました。

安心・安全な未来社会はキャンパスから動き出している
阪口啓 副学⾧(研究戦略・研究企画支援担当)・工学院教授
工学院の阪口啓教授は、VI:Innovative-Life Society「サイバー・フィジカル空間で共創社会を開拓する」のもとで取り組む、デジタルツイン技術を基盤とした未来社会づくりについて語りました。
阪口教授は、自動運転に向けて「モビリティ・デジタルツイン」を構築し、センサやクラウド技術を通じて車両や歩行者の動きをリアルタイムで把握・予測する仕組みを大岡山キャンパス内で実現しています。これを活用し、事故予防や渋滞緩和、移動困難者の支援など、社会課題の解決に向けた研究が進められています。
阪口教授は、技術を「研究」から「実装」へと押し出す覚悟をにじませて、こう語りました。「研究者だけでは社会は変えられません。産業界、行政、国際機関、そして多様な人々との協働が不可欠です。技術を社会に実装することで人々の暮らしをより良くしていく―これが私たちの挑戦です」

地球と宇宙をつなぐ共創のフロンティア
関根康人 未来社会創成研究院教授
未来社会創成研究院の関根康人教授は、VI:Space Innovation「宇宙生活圏を開拓する」のプログラム・ディレクターとして、地球と宇宙をつなぐ研究の最前線を紹介しました。
「宇宙開発は今や『アポロ3.0』と呼べる新たな段階に入っています。単に宇宙へ行く時代から、宇宙で持続的に生きる社会を築く時代です」と語り、NASAのアルテミス計画や、SpaceX、Blue Originなど民間企業の参入により、宇宙産業が急速に拡大している現状を説明しました。
さらに、「宇宙開発や宇宙進出は、決して遠い未来の話ではありません」と強調。火星の氷を利用したエネルギー生成、人工光合成による生命維持技術、生体センサを活用したリモート医療など、宇宙と地上の課題を同時に解く多様な技術開発が進んでいることを紹介しました。
そして、「なぜ宇宙へ行くのか(Why)」「どう生きるのか(How)」という根源的な問いを軸に、Science Tokyoが挑む方向性を語りました。

関根教授はまた、宇宙で生まれる技術が地上の医療や福祉にも応用される可能性を指摘し、国内外の企業との共創によるエコシステム形成が活発に進んでいることを紹介。Science Tokyoは、地上でも宇宙でも、人が健康で幸福に挑戦し続けられる社会の実現を目指すと語りました。
地球の未来を支える、エネルギーの転換点
後藤美香 環境・社会理工学院教授
米国出張中のためボストンからオンラインで登壇した後藤美香教授は、国内外の機関と連携し、エネルギーと環境をテーマとする研究を進めています。VI:GX Frontier「グリーントランスフォーメーションで持続可能な未来を実現する」のもと、気候変動、再生可能エネルギー、自然資本の回復など地球規模の課題に取り組む研究を紹介しました。
「経済性と環境性の両立こそが、持続可能な社会の鍵なのです」と力強く語り、環境価値を社会システムに組み込む必要性を訴えました。自身の専門であるエネルギー経済学の視点から、分散型エネルギー資源と電力市場の活用や、V2G(Vehicle to Grid)技術など、経済と環境を結ぶ新たなモデルを次々と紹介しました。
そして、「研究成果を社会に還元し、環境価値を評価する仕組みを共に築くこと―それこそが私たちが目指す未来のGXです」と結びました。
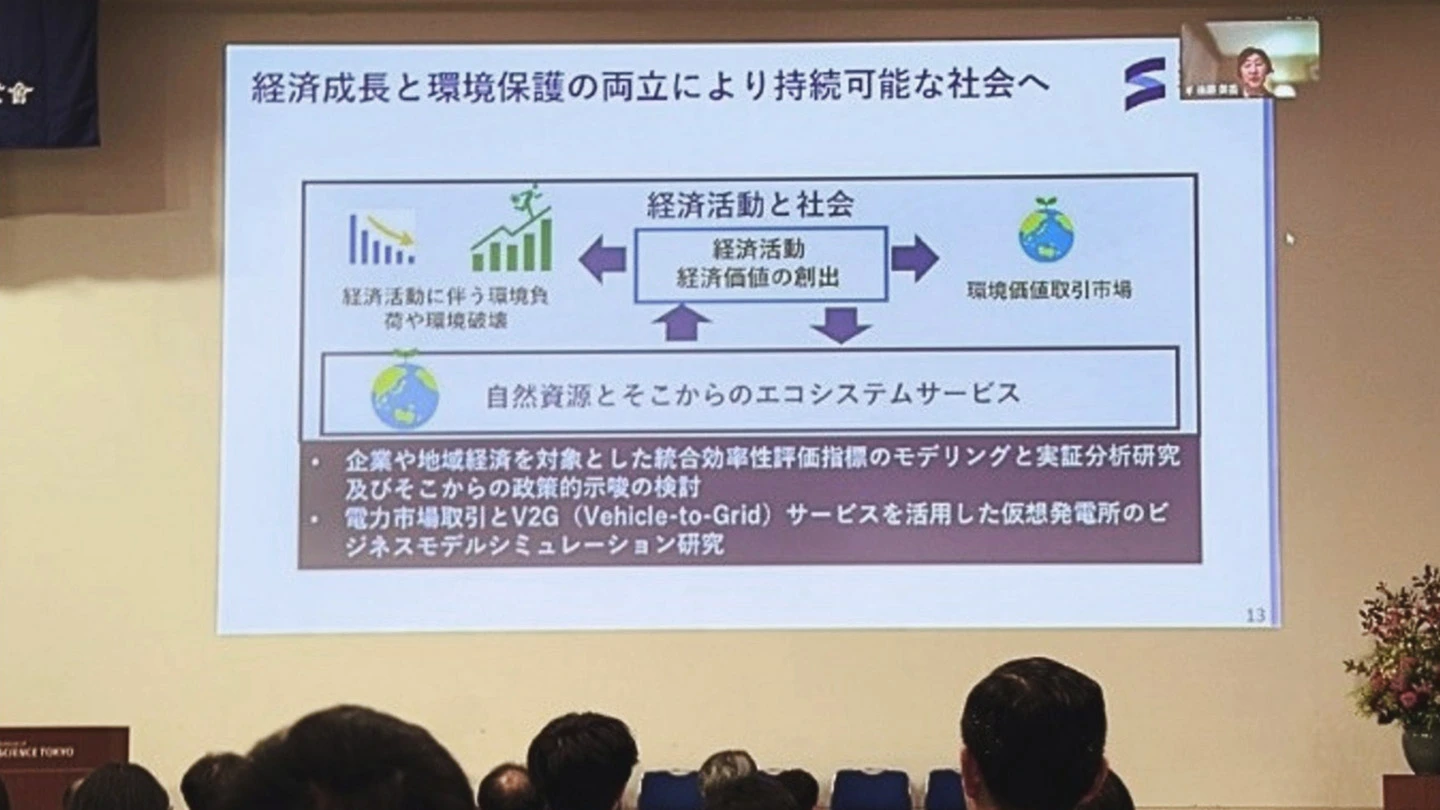
科学で命と暮らしを守る
石野智子 医歯学総合研究科 教授
医歯学総合研究科の石野智子教授は、VI:Resilience-Tech Society 「災害・パンデミックにレジリエントな社会を実現する」のもと、科学の力で命と尊厳を守る社会づくりを目指すビジョンを紹介しました。レジリエンスとは、災害や感染症の被害を最小限にとどめ、人々の生活への影響を減らし、しなやかに対応する力を指します。
石野教授は、災害や感染症を完全に防ぐことはできないという現実を踏まえ、被害を科学の力で減らし、迅速な回復を支えることの重要性を強調しました。
また、感染症対策は一つの国だけでは完結しない課題であり、国際的な協働が不可欠であるとし、アフリカ諸国との連携による感染症データの解析や、ウイルス検出デバイス開発などの取り組みを紹介しました。自身の専門であるマラリア研究では、遺伝子改変技術を用いて感染経路やワクチン標的タンパク質を特定し、皮膚内でのマラリア原虫の移動を阻害する新たなワクチン開発を進めています。そして講演の締めくくりに、石野教授は強い決意を込めてこう語りました。

「どの国にも取り残される命があってはなりません。科学と国際協働の力で、地球規模のレジリエンスを築いていきたいのです」
質疑応答と閉会
各講演後には活発な質疑応答が行われ、卒業生や一般の参加者から多彩な質問が寄せられました。
「心をどのように科学的に捉えられるのか」という問いに対しては、廣田副理事・副学長が「永遠の謎かもしれない」としながらも、脳科学の視点から心の仕組みを説明しました。科学が人の内面に迫る挑戦に会場の関心が集まりました。
石野教授のセッションでは、マラリア研究や感染症対策に加え、「真夏に蚊を見かけなくなったのはなぜか」「遠い南の国に生息する蚊が日本にやってくる可能性はあるか」といった身近な話題にも質問が及びました。石野教授が遺伝的適応や気候変動の影響を交えて説明すると、会場からは感嘆の声が上がりました。
最後の全体質疑では、大学と社会がどのように連携して未来を築いていくかに関心が寄せられました。
波多野理事は、講演で示した“ともに未来を創る”という考えを踏まえ、その実現に向けた具体的な仕組みとして「ビジョナリーパートナーズ制度(仮称)」を構想していると説明しました。


本セミナーは、VIが掲げるビジョンに向けた挑戦が、研究現場から社会へと広がり始めていることを実感する機会となりました。
Science Tokyoは今後も、「善き未来」に向けて、多くの皆様とともに未来を創っていきます。
関連リンク
お問い合わせ
- 備考
- 研究支援窓口