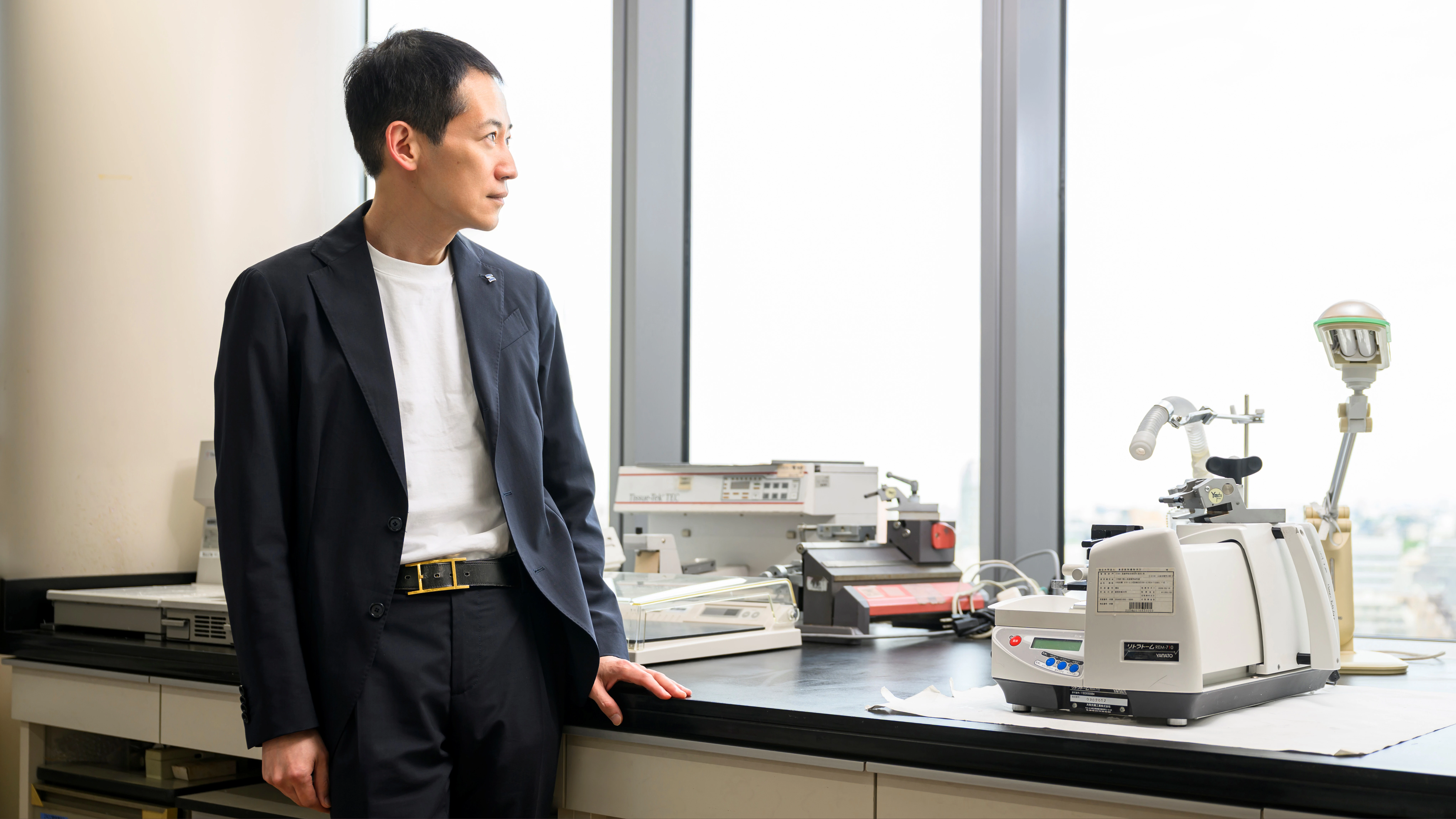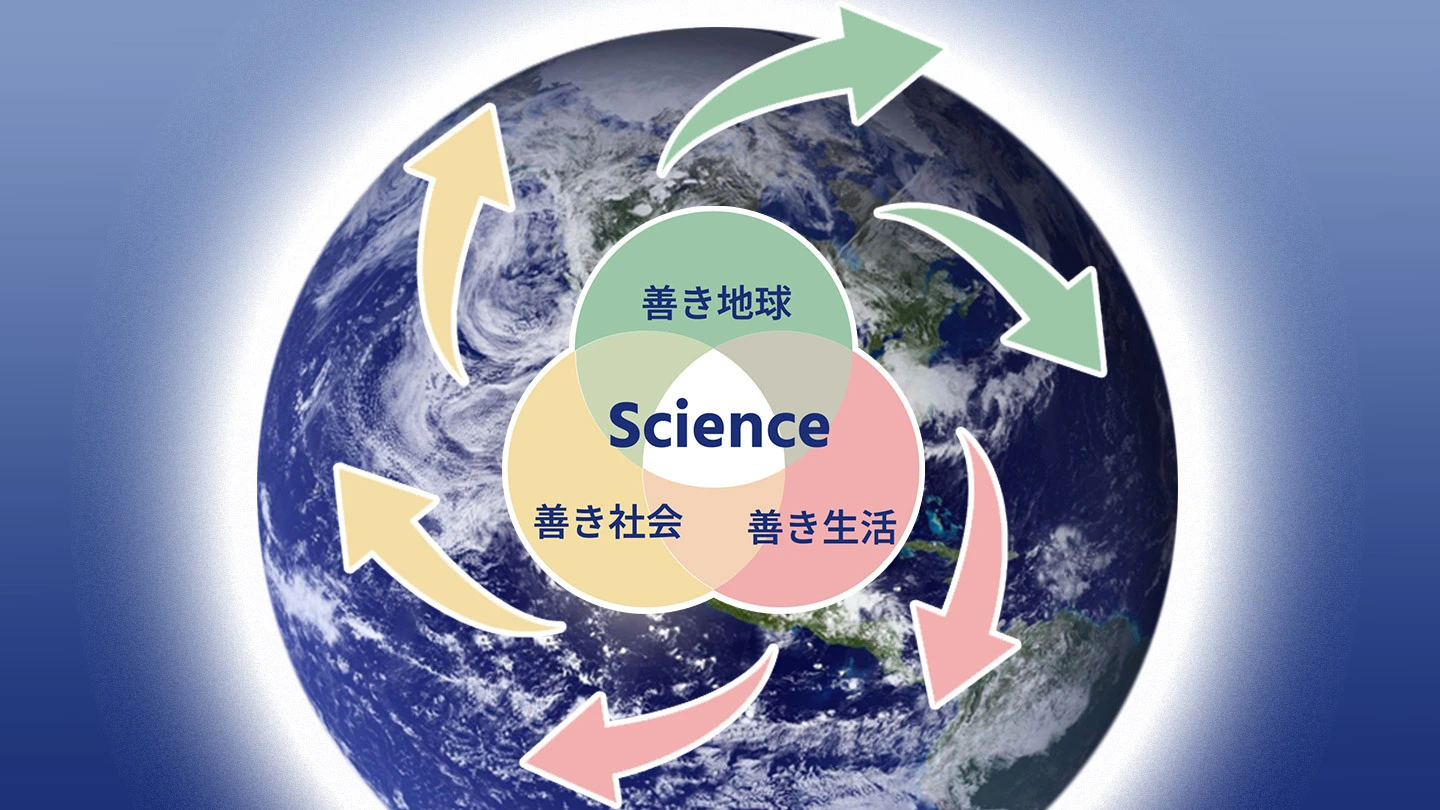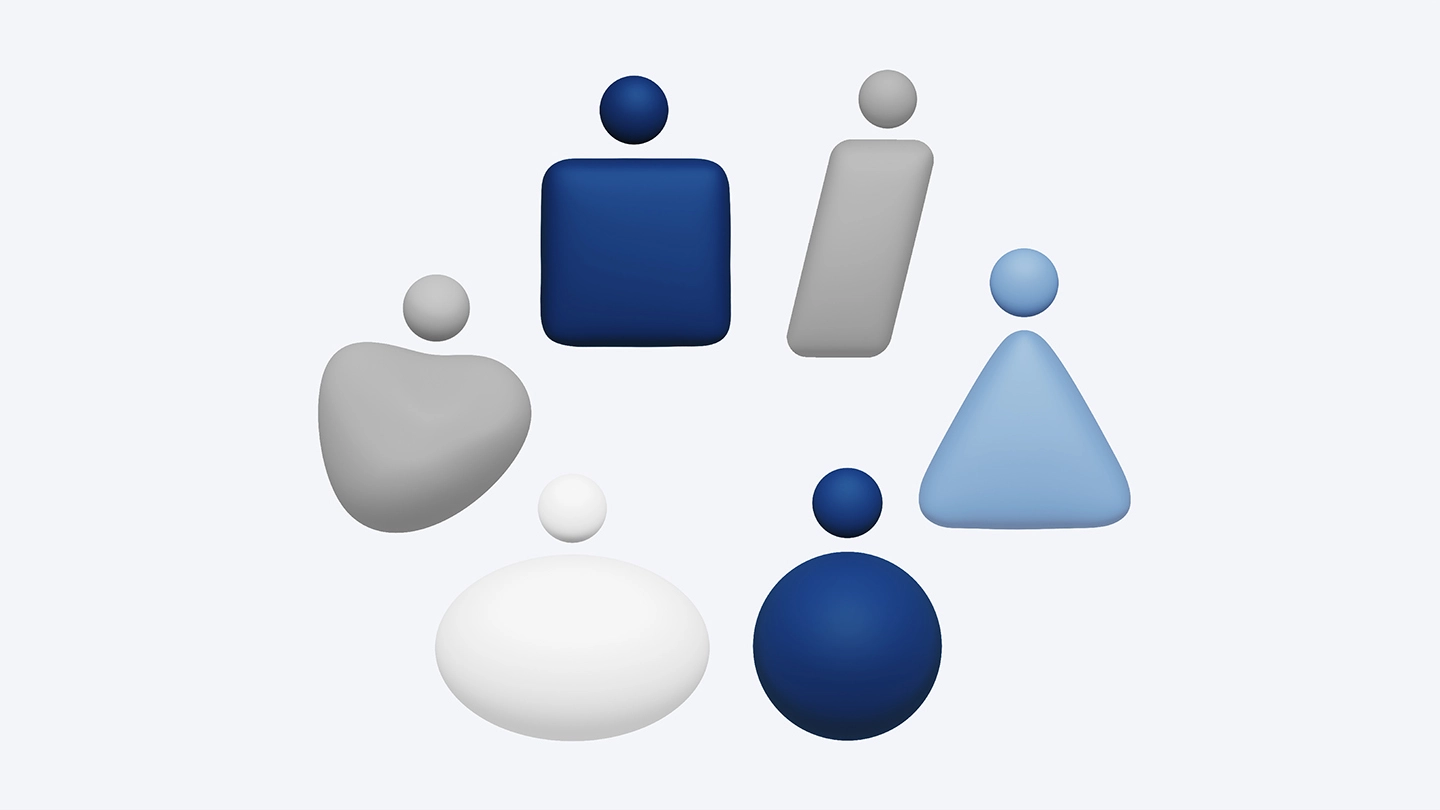東京科学大学(Science Tokyo)は、「『科学の進歩』と『人々の幸せ』とを探求し、社会とともに新たな価値を創造する」を大学のMissionとして掲げ、その実現に向けた分野横断・融合型の研究体制「Visionary Initiatives(VI)」を2025年に始動させました。現在、6つのVIが「善き生活」「善き社会」「善き地球」という3本柱を軸に、社会変革の姿と共通ビジョンをそれぞれが描き、未来を切り拓く挑戦をすでに始めています。
今回はその一つ、GX Frontier「グリーントランスフォーメーションで持続可能な未来を実現する」を率いる環境・社会理工学院の後藤美香教授に、VIのあり方や新たな価値創造、そして今後の展望について語ってもらいました。
わたしたちの未来を変える力が、ここに集結
GX Frontierを率いる立場として、どんな課題や期待を見据えていますか?
後藤
「GX Frontier」は、地球と調和しながら人々が健康で快適に暮らせる世の中のために、グリーントランスフォーメーションで持続可能な未来を実現することを目指しています。例えば地球環境やエネルギーの問題のように、多様な分野を総合して取り組むことが求められるテーマです。
現時点で49人の研究者が4つの将来像-「気候変動の課題克服」「地球モニタリングによる最適解の探究」「新たなエネルギー・資源の開拓」「ネイチャーポジティブの実現」-に関連する研究を推進しています。それらは「グリーンホスピタル(GX Frontierが目指す一つの形。再生可能エネルギーや省エネ技術を最大限に活用し、環境にやさしく持続可能でありながら、高度な医療機能を備えた未来型病院)」への社会実装でつながっています。
メンバーの専門分野は細分化されていて、それぞれが特徴ある研究を自在に展開しています。各メンバーの研究に対する思い、個々の目標、時間軸や課題認識は多様ですが、「持続可能な地球を実現する」というVIの共通のビジョンが大きな柱となって結集し、未来に挑む大規模なプロジェクトへと発展していくことを期待しています。
Visionary Initiative: GX Frontier 「グリーントランスフォーメーションで持続可能な未来を実現する」
GX Frontierでは、新たな科学技術の英知を融合し、地球との調和のもとで繁栄できる未来を目指します。

・化石燃料に依存しない社会
・高度なエネルギー貯蔵技術の開発でエネルギーの供給を安定化
・再生可能エネルギーを主力電源に
・温室効果ガスの排出削減・回収・活用でカーボンニュートラルに

・気候変動、環境汚染、生態系のリアルタイムデータ分析と対策
・デジタル仮想地球を使ったシミュレーションと未来環境予測
・生物の環境適応力の解明と、それを活かした適応能力の強化や応用

・未開拓の海底資源の活用
・細胞や微生物が持つエネルギー生産の仕組みを理解し、かつてない新エネルギーを開発へ
・宇宙空間で太陽光発電を実現
・月と火星の資源探査と開拓
・脳のエネルギー消費の仕組みを利用しAIやロボットの省エネルギー化を実現

・生物の棲息環境を保護するためにごみや環境破壊を減らした循環型社会の構築
・環境保護と経済成長を両立させる人間活動の実現
・都市公園、屋上緑化など自然の力を活かした都市型自然調和社会
多様な価値を考える新しい社会へ
研究の先に、どんな社会を思い描いていますか?
後藤 4月に開催されたScience Tokyo設立記念シンポジウムでは、GX Frontierが目指す未来を実現するにあたって、すでに進行中の研究として、「グリーンエネルギー化に向けた必須技術の研究」「衛星データを用いた大気汚染評価システム」「脳の情報処理過程から学ぶ人工知能の省エネ化」「生物多様性と社会的要因の統合評価」「持続可能な社会のための経済と環境の総合的評価指標・評価体系の構築」を紹介しました。例えば、脳は非常にエネルギー効率のよい情報処理システムです。AIの活用で膨大な電力が必要になる中、脳の情報処理の仕組みからヒントを得てAIを省エネ化できれば、世界を変える技術になる可能性があります。
わたしの研究テーマは、社会システムにおける経済性と環境性の追求です。例えば、太陽光や風力といった再生可能エネルギーや、水素エネルギーは、利用時に二酸化炭素を出さず、地球温暖化防止に役立つという点で環境的に望ましいものの、コストが依然として高いことや、天候や季節によって供給が安定しないため、経済面で課題があります。しかし、持続可能な社会を実現する上で、経済性の追求がすべてではありません。「環境」「レジリエンス」「ダイバーシティ」といった価値を社会システムに組み込み、評価軸を拡張していくことが求められます。従来の経済性という評価基準のみでは十分に考慮されてこなかった環境性や社会性といった要素を体系的に取り込み、システムの評価に反映させることで、新しい社会像を描き出せると考えています。

出会いが生みだす価値と未来に向けた挑戦
異分野の研究や社会との対話から、どんな新しい可能性が見えてきますか?
後藤
わたしはエネルギーの研究を社会科学の視点から行っていますが、異分野の研究者と話してみて、意外な接点があることに気づくことがあります。例えば、経済の問題はハードウェアを扱うような工学系の研究者にとってはあまり関心がない部分だろうと思っていましたが、「そこは重要なポイントです。技術がいかに優れていても、経済性を考慮しなければ社会には広まらないですからね」と共感していただいたのです。お互いの研究やその背後にある考え方を知ることの大切さを実感しました。
現代は、地球温暖化や気候変動の問題が顕在化し、環境保全や自然エネルギーへの転換が、人々の価値観や社会の動きと合致する大きな潮流になっています。そのような社会全体の変化が、研究の方向性に影響を及ぼす局面はあります。
例えば、かつては経済性や安定性の問題から普及の難しさがしばしば取り上げられてきた風力や太陽光などの再生可能エネルギーですが、技術開発の進展によって電力供給の主力の一つになってきたように、今はまだ十分に認識されていない要素が、新しい価値として芽を出し、社会へ広がっていくことがあります。そのような、未来を変革する可能性を秘めた要素がVI GX Frontier内にもたくさんあります。それが未来の社会を動かしていくと思うととてもエキサイティングです。
研究は社会に影響を及ぼし、新しい価値や社会の仕組みを生み出します。研究と社会が相互に作用し合い、新たな潮流や未来像を形づくっていく。そのダイナミックなプロセスを築けることに、大きな意義と魅力を感じています。
変化の大きい世界情勢を、研究者としてどう見ていますか?
後藤 GX Frontierが取り扱う「地球温暖化」や「気候変動」に関する研究は、人類にとって喫緊の課題であるとともに、長期にわたる影響を有するものです。その時々の社会の変化や不確実性への対処はあるものの、1、2年単位の動向にとらわれず、未来を見据えて研究を継続することが肝要です。研究者は長期的な視点で研究に取り組む責任がありますし、そのためにはそれが可能な研究環境が必要です。
知の結びつきが無限の可能性を生む
多様な個性が集まるダイバーシティの力を、今後どのように研究や社会へ生かしていきたいですか?
後藤
例えば、今回、Science Tokyoで始動したVI体制では、6人のPDのうち3人は女性ですが、ダイバーシティは組織の活力の源です。同じ背景や特性を持つ人ばかりが集まると、変化が起こりにくく、活力を失う危険もあります。VIには多様な個性を持つ研究者が集まっています。さまざまな交流を通じてお互いの理解が深まり、思いがけない知の結びつきが生まれることを期待しています。
2024年10月に東京工業大学と東京医科歯科大学が統合し、Science Tokyoが誕生しました。長い歴史と名声を持つ二つの大学が統合したことで、これまで以上に無限の可能性が広がっています。VIを通じて「わたしたちが新しい大学の名を世界に轟かせる」という意気込みで挑みたいと思います。
取材日:2025年8月4日(オンラインZoomにて)
プロフィール

関連リンク
更新履歴
- 2025年9月24日 関連リンクを追加しました。
- 2025年9月19日 関連リンクを追加しました。
お問い合わせ
研究支援窓口