ポイント
- 脳卒中患者はリハビリテーション中に嚥下障害が生じやすく、回復期病院では摂食嚥下リハビリテーションが行われていますが、睡眠関連呼吸障害(SDB)は注目されていませんでした。
- 本研究では、回復期病院に入院する脳卒中患者91名に対して睡眠検査と嚥下機能の評価を実施した結果、SDBを有する患者の割合が高く、嚥下機能との関連が確認されました。
- 脳卒中後の回復期リハビリテーションにおいて、睡眠の重要性に注目することで、回復期病院における歯科医師の役割がさらに広がり、より包括的なリハビリテーション支援が期待できます。
概要
東京科学大学(Science Tokyo)※大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野の戸原玄教授、山口浩平講師、柳田陵介医員らの研究チームは、脳卒中発症後、リハビリテーションを目的として回復期病院[用語1]に入院した患者を対象に、睡眠検査および嚥下機能評価を行いました。その結果、回復期病院に入院中の脳卒中患者において、睡眠関連呼吸障害(SDB)[用語2]を有する者の割合が高いこと、またSDBの重症度が経口摂取度と関連することを明らかにしました。
SDBとは、睡眠中に呼吸が止まったり浅くなったりする状態です。SDBがあると、脳卒中のリスクが増加します。一方で、嚥下障害[用語3]は、脳卒中などの疾患や加齢によって食物が飲み込みにくくなる障害であり、重症化すると食形態の制限や経管栄養が必要になる場合もあります。本研究では、SDBの重症度をApnea Hypopnea Index(AHI)で、食形態の指標をFunctional Oral Intake Scale(FOIS)でそれぞれ評価し、これらの関連を統計解析で検討しました。
日本では、歯科医師は嚥下障害およびSDBの両方に対応しています。しかし、これまで回復期病院においては睡眠に対する注目がありませんでした。SDBを有する患者には、舌や口蓋扁桃、軟口蓋などに口腔内の特徴が見られるため、嚥下障害に対応する歯科医師がSDBに気づき、適切な介入につなげられる可能性があります。反対に、睡眠に精通した歯科医師が嚥下機能の低下にも気づくことができるなど、嚥下障害とSDBの両面を考慮した歯科医師による回復期医療へのさらなる貢献が期待されます。
本研究の成果は、11月7日(現地時間)に「Journal of Prosthetic Dentistry」誌に掲載されました。
- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景
睡眠関連呼吸障害(SDB)は、高血圧や糖尿病、高脂血症などの生活習慣病だけでなく、脳卒中のリスクも高める要因とされています。過去の研究によると、SDBがある場合、脳卒中の発症率が2~4倍に増加することが報告されています。また、脳卒中後には高い確率で嚥下障害が生じることが知られています。咽頭の筋肉や舌骨などの身体の構造物は、嚥下と睡眠の両方に関与しているため、脳卒中患者においてSDBと嚥下障害には関連があると考えられてきましたが、これまで回復期病院における脳卒中患者を対象とした調査は行われていませんでした。
脳卒中患者の中にはSDBを有する割合が高いものの、医師が睡眠に関する質問を行う、もしくは睡眠検査を行う割合はそれぞれ6%、9%と低いことが過去の報告で示されています。脳卒中患者におけるSDBは、不良な転帰と関連しているものの、SDBのスクリーニングは一般的ではありません。一方、歯科医師は回復期病院において日常的に入院患者の口腔内診察や嚥下機能の管理を行っていることから、SDBを発見し、その後の介入につなげられる可能性があります。
本研究では、回復期病院に入院中の脳卒中患者を対象に、SDBの有病率およびSDBと嚥下障害の関連を明らかにしました。
研究成果
本研究の対象者は、2021年8月から2024年3月の間に脳卒中と診断され、千葉県内のリハビリテーション病院(回復期病院)に入院した患者140名(平均年齢:73.3±12.4歳、男性78名)でした。対象者は入院後、睡眠検査装置であるWatchPATを用いて就寝中に睡眠検査を行いました。このうち91名(平均年齢:72.3±12.7歳、男性50名)において睡眠検査を完了し、解析の対象となりました。また診療録から、年齢、性別、肥満度を示すBody Mass Index(BMI)、意識レベルを示すJapan Coma Scale(JCS)、脳卒中の重症度を示すmodified Rankin Scale(mRS)、既往歴を示すCharlson Comobidity Index(CCI)、経口摂取レベルを示すFunctional Oral Intake Scale(FOIS)といったデータが収集されました。
睡眠検査の結果、就寝中に1時間あたりの無呼吸・低呼吸回数を示すApnea Hypopnea Index(AHI)が測定されました。その結果、対象者の93.4%がAHIが5以上、つまりSDBであることが確認されました。また、FOISが6以下、すなわち食事形態を調整(刻む、柔らかくするなど)する必要があるか、経管栄養が必要な70名(平均年齢:72.0±13.1歳、男性39名)に限ると、SDBを有する割合が95.7%に達していました。
次に、SDBの重症度と経口摂取レベルの関連を検討するため、多変量解析を行いました。その結果、年齢、性別、BMI、JCS、mRS、CCIといった因子を調整した上で、FOISがAHIと関連していることが明らかになりました。
本研究の結果から、回復期病院に入院する脳卒中患者において、FOISが低い、すなわち食事形態の調整や経管栄養を必要とする程度が高い患者ほど、SDBが重症である可能性が示唆されました。
社会的インパクト
本研究は、回復期病院における脳卒中患者のSDBの割合およびSDBと嚥下障害の関連を明らかにした初めての研究です。歯科医師は口腔内を診察するだけでなく、回復期病院での摂食嚥下リハビリテーションにも携わっているため、舌や口蓋扁桃、軟口蓋などSDBの要因となりうる口腔内の特徴に気づき、適切な介入につなげられる可能性があります。これまで回復期病院では睡眠に注目されることがありませんでしたが、嚥下障害とSDBの双方の視点から歯科医師が脳卒中患者に関与することで、回復期病院でのリハビリテーション医療への貢献度がさらに高まると考えられます。
今後の展開
今回の研究では、回復期病院への入院時の横断研究を実施しました。今後は、入院時から退院時までの縦断的な解析や、口腔・嚥下機能管理を行う歯科医師によるSDBスクリーニングの有効性、また嚥下障害とSDBの双方を管理することがリハビリテーションに与える影響について、さらなる検討を進めていきます。
用語説明
- [用語1]
- 回復期病院:脳卒中や骨折などの疾患で急性期を経過した患者が、身体機能の回復を図るためにリハビリテーションを行う病院。
- [用語2]
- 睡眠関連呼吸障害(SDB):睡眠中に呼吸が止まる、もしくは浅くなる障害。睡眠が妨げられることにより、起床時の頭痛や日中の眠気、倦怠感などを引き起こすほか、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクを上昇させる。
- [用語3]
- 嚥下障害:病気や加齢により、食べ物や飲み物が飲み込みにくくなる、もしくは誤って気管に入りやすくなる障害。嚥下障害に対して回復期病院では、飲み物にとろみをつける、食べ物を刻む、などの食形態の調整が行われる。
論文情報
- 掲載誌:
- Journal of Prosthetic Dentistry
- 論文タイトル:
- Sleep apnea and dysphagia in patients after a stroke recovering in convalescence rehabilitation
- 著者:
- Ryosuke Yanagida, Kohei Yamaguchi, Kazuharu Nakagawa, Kanako Yoshimi, Takami Hino, Ayumi Kisara, Haruka Tohara
研究者プロフィール
山口浩平 Kohei YAMAGUCHI
東京科学大学 大学院医歯学総合研究科
摂食嚥下リハビリテーション学分野 講師
研究分野:高齢者歯科、摂食嚥下リハビリテーション

柳田陵介 Ryosuke YANAGIDA
東京科学大学 大学院医歯学総合研究科
摂食嚥下リハビリテーション学分野 医員
研究分野:高齢者歯科、摂食嚥下リハビリテーション
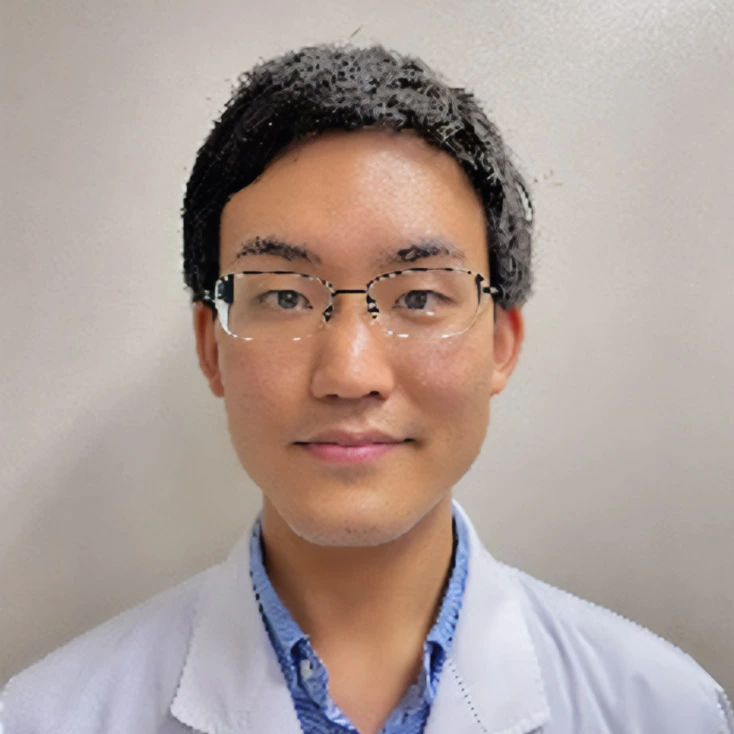
戸原玄 Haruka TOHARA
東京科学大学 大学院医歯学総合研究科
摂食嚥下リハビリテーション学分野 教授
研究分野:高齢者歯科、摂食嚥下リハビリテーション

関連ページ
お問い合わせ
取材申込み
東京科学大学 総務企画部 広報課
- Tel
- 03-5734-2975
- Fax
- 03-5734-3661
- media@ml.tmd.ac.jp