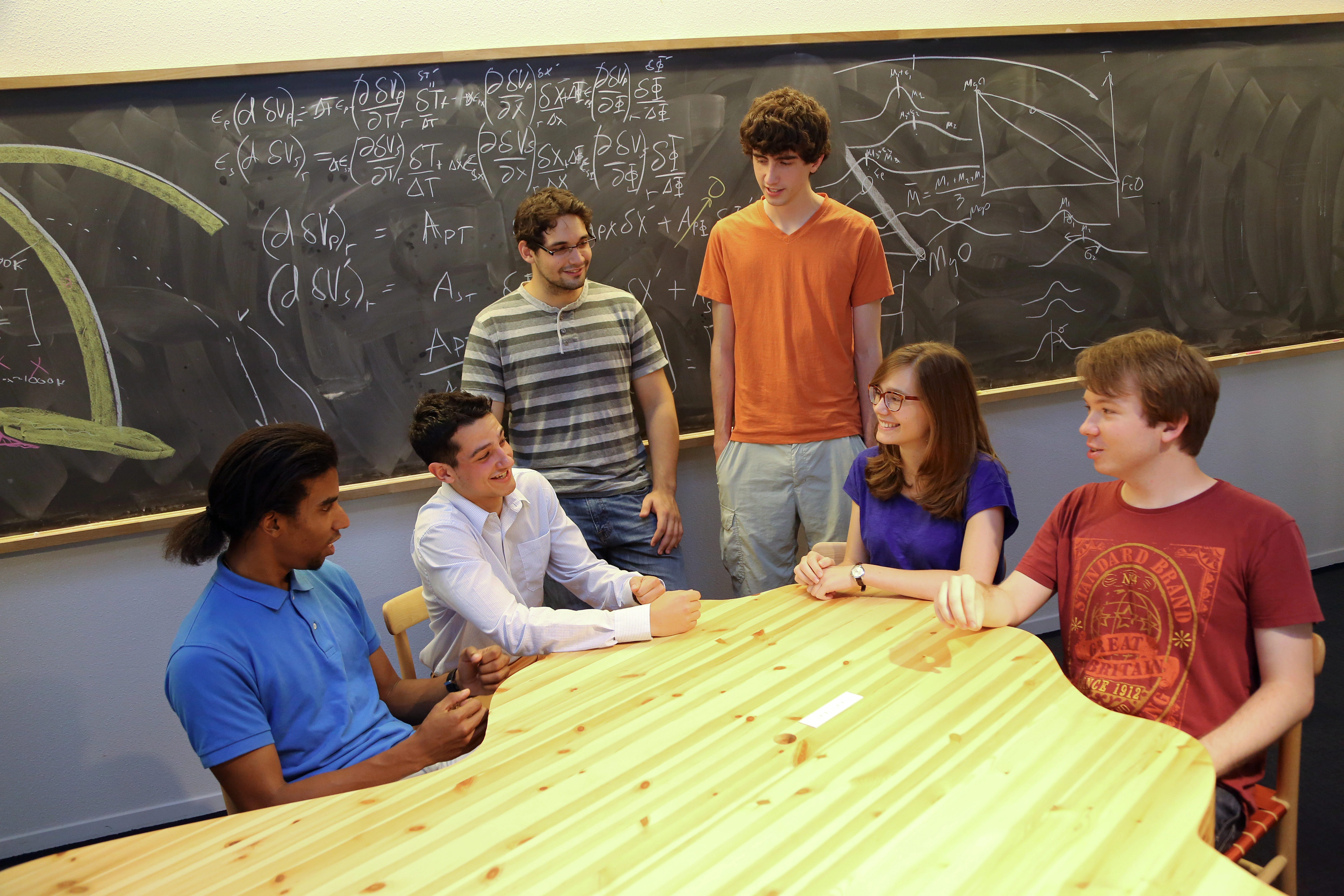どんな研究?
人工光合成は、地球の未来を支える切り札として期待されている技術です。植物が太陽の光で水と二酸化炭素から酸素や栄養を効率よくつくるように、太陽光を使って水から水素を取り出したり、二酸化炭素をエネルギー源となる物質に作り替えるのです。そして、その反応の中心的な役割を果たすのが「光触媒」と呼ばれる材料です。
2010年代に入ってからは、鉛(Pb)やビスマス(Bi)を含むオキシハライド(酸ハロゲン化物)という物質が光触媒として注目を集めました。その中でも Pb₂Ti₂O₅.₄F₁.₂(PTOF) という物質は、水を分解して水素を生み出すことができる安定した光触媒として知られていました。ただし、反応の効率が低く、実用化のために必要なレベルの水素や燃料を得るにはまだ力不足でした。

これまでのオキシハライド光触媒の研究では、粒子を小さくすることで反応効率が上がる可能性があるものの、光触媒作用にとって重要な電子の寿命が短くなるために性能が落ちるとされてきました。光触媒の結晶中で原子の並びの乱れや欠損があると、一般的に電子の寿命は短くなってしまいます。ナノ粒子のような小さな物質ではこうした原子配列の乱れや欠損が生じやすいため、高効率な人工光合成反応に利用できるオキシハライド光触媒のナノ粒子化は未開拓のまま残されていました。
ここが重要
東京科学大学(Science Tokyo)の前田和彦(まえだ・かずひこ)教授らを中心とする研究チームは、PTOFという光触媒を、特殊な方法でナノサイズ(数十ナノメートル、髪の毛の太さの1万分の1程度)にすることに成功し、光触媒としての性能が大幅に向上するという事実を見出しました。
ナノサイズにすると粒子の表面積が広がり、光が当たったときに生まれる電子や正孔(プラスの電荷)が化学反応に参加しやすくなります。従来は、「小さくすると寿命が短くなって逆効果」と考えられていましたが、今回の成果はそれを覆すものでした。その結果、水素の発生量は10倍以上に増えました。
さらに、改良した光触媒では、「量子収率」という光の変換効率を示す指標が15%以上に達しました。これは、受けた光のエネルギーのうち10数%が水素生成などの反応に使われていることを意味し、オキシハライド光触媒としては当時報告されていた中で最高の値でした。
今後の展望
この成果は、人工光合成の実現に向けて大きな一歩です。太陽のエネルギーを直接利用して、クリーンな水素燃料や、二酸化炭素を資源に変える技術にまた一歩近づきました。将来は、再生可能エネルギーと組み合わせて、大気中のCO₂を減らしながら燃料をつくる「カーボンリサイクル社会」につながるかもしれません。
また、「粒子の形や大きさを調整することが光触媒性能を左右する」という知見は、これからの光触媒開発、特にオキシハライドのような新しいタイプの光触媒の開発に大きなヒントを与えるでしょう。
研究者のひとこと
身近にあるありふれた物質から、人類の役に立つ新しい物質を生み出せる―それが人工光合成の大きな魅力です。二酸化炭素も、これまでは厄介者として扱われることが多かったのですが、資源として有効に使える可能性が見えてきています。
もちろん、人工光合成の分野にはまだ多くの難しい課題があり、腰を据えた長期的な研究が欠かせません。私は学生時代から20年以上この研究に携わってきましたが、量子収率などの研究レベルは当時に比べて飛躍的に向上した一方で、社会実装に向けて越えなければならない壁は今も残っています。
これから先の10年から30年が、この技術の未来を決める正念場だと感じています。若い学生の皆さんと力を合わせながら、循環型社会の実現に向けて研究を進めていきたいと思います。
(前田和彦:東京科学大学 理学院 化学系 / 総合研究院 自律システム材料学研究センター 教授)

この研究をもっと詳しく知るには
お問い合わせ先
研究支援窓口