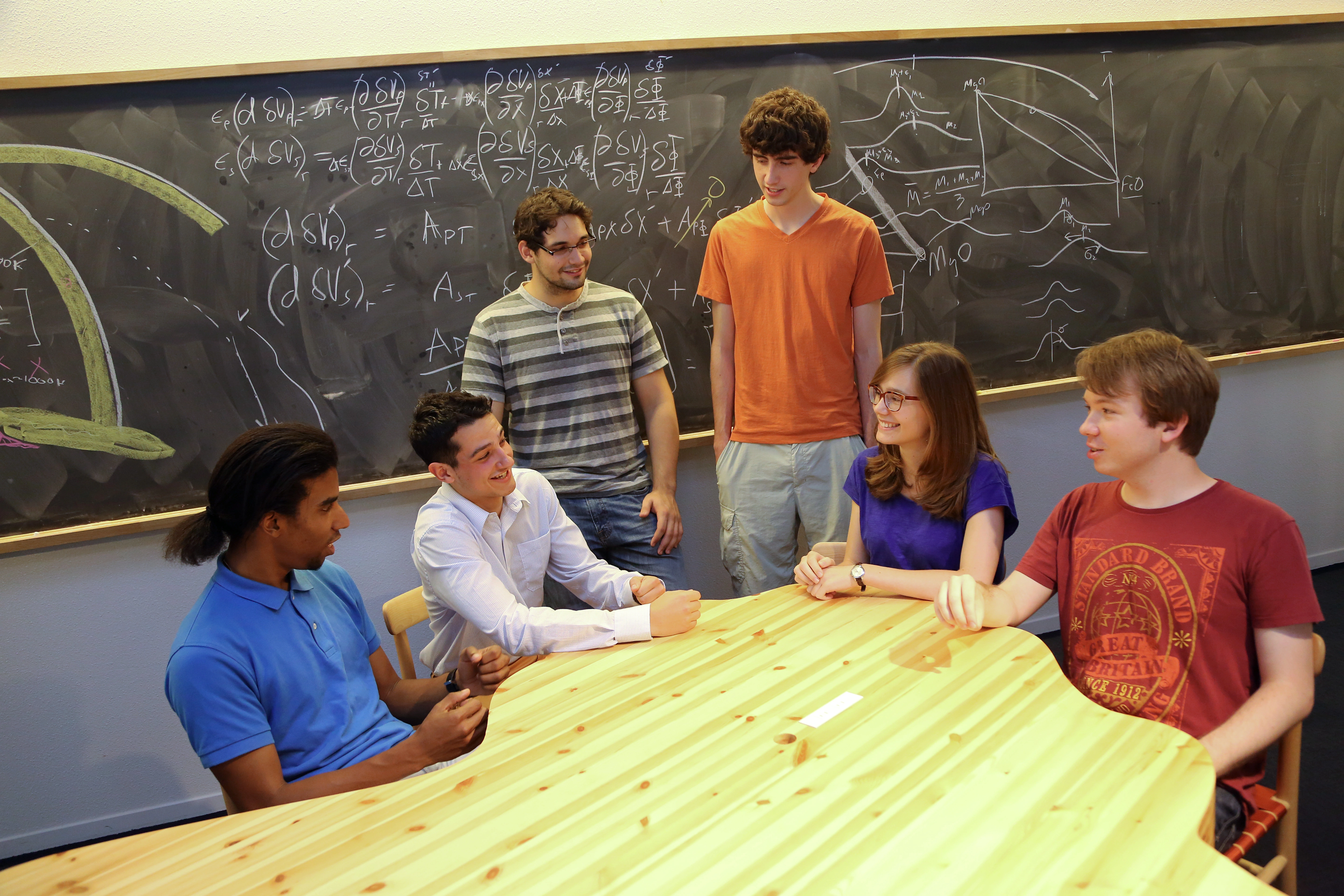どんな研究?
人は誰でも人生の最期を迎えます。そのとき、残された家族には大きな心の負担がかかります。だからこそ、亡くなる前に心の準備をしたり、やり残したことを整理するためのサポートがとても大切です。日本では高齢化が進んでおり、こうしたケアや家族支援の重要性が高まっています。しかし、どのように支援すればよいか、決まった方法はありません。
これまでは、死別後の家族の心の回復や、故人とのつながりが注目されてきましたが、家族と医療関係者がどう協力し合うかについての指針はほとんどありませんでした。

そこで東京科学大学の杉原太郎(すぎはら・たろう)准教授と博士後期課程3年の齋藤駿(さいとう・しゅん)さんは、終末期ケアの現場で家族と医療者が一緒に関わるときに、どんな課題があるのかを探り、課題解決にむけて科学技術ができる支援を考えていく基礎情報とするために、インタビュー調査と分析を行いました。
ここが重要
インタビュー調査では、聞き手が投げかける質問が答えに影響しないようにする工夫に最大限の注意を払いました。これは、目的があって行う一般的なインタビューのように、聞き手の意図や意識が回答に反映されてはならないからです。
もちろん終末期ケアというテーマを設定しましたが、様々な意見や気持ちが言語として収集できるインタビュー技術が重要でした。これによって、膨大な言葉の情報から研究目的に活用できる内容を効率的に抽出する分析が可能になったのです。
分析の結果、家族の思いと医療従事者の支援がすれ違い、意図しない方向へケアが進んでしまうことがあることが浮き彫りになりました。そして、家族が本来意図していなかった役割を引き受けることになり、強い感情的ストレスを感じる事態へと進行していく現状が見えてきました。杉原准教授らは、このような状況を「意図せず、滲み出てくる作業」と名付け、次の3つに分類しました。
(1)病気を本人に伝えず世話を続けた結果、家族が心身ともに疲れてしまう「過剰な仕事」
(2)最期の願いを叶えられず、後悔をかかえる「見落とされた仕事」
(3)医療者の善意が家族の意向と食い違い、かえって負担になる「越権的な仕事」
今後の展望
「意図せず、滲み出てくる作業」は、これまで見過ごされてきた家族支援のチャンスともいえます。
分類された3つの仕事を防ぐために必要となる対策は異なるはずです。こうした状況を見つめ直すことで、よりよい終末期ケアの実現につながる新しい技術やそれを活用した支援策が生まれることが期待されます。
超高齢社会を迎える日本にとっても、重要な手がかりになる研究です。
研究者のひとこと
終末期ケアでは、家族と医療者のあいだの小さなすれ違いが、後になって深い後悔につながることがあります。この研究は、そのすれ違いの原因や背景を丁寧に掘り下げ、よりよい支援の形を見つける手がかりを探ろうとするものです。
現場の声を聞くことから見えてきた課題を、科学技術が寄り添う支援の在り方を考え、その流れを育んでいきたいと考えています。
(杉原太郎:東京科学大学 環境・社会理工学院 イノベーション科学系 准教授)
この研究をもっと詳しく知るには
お問い合わせ先
研究支援窓口