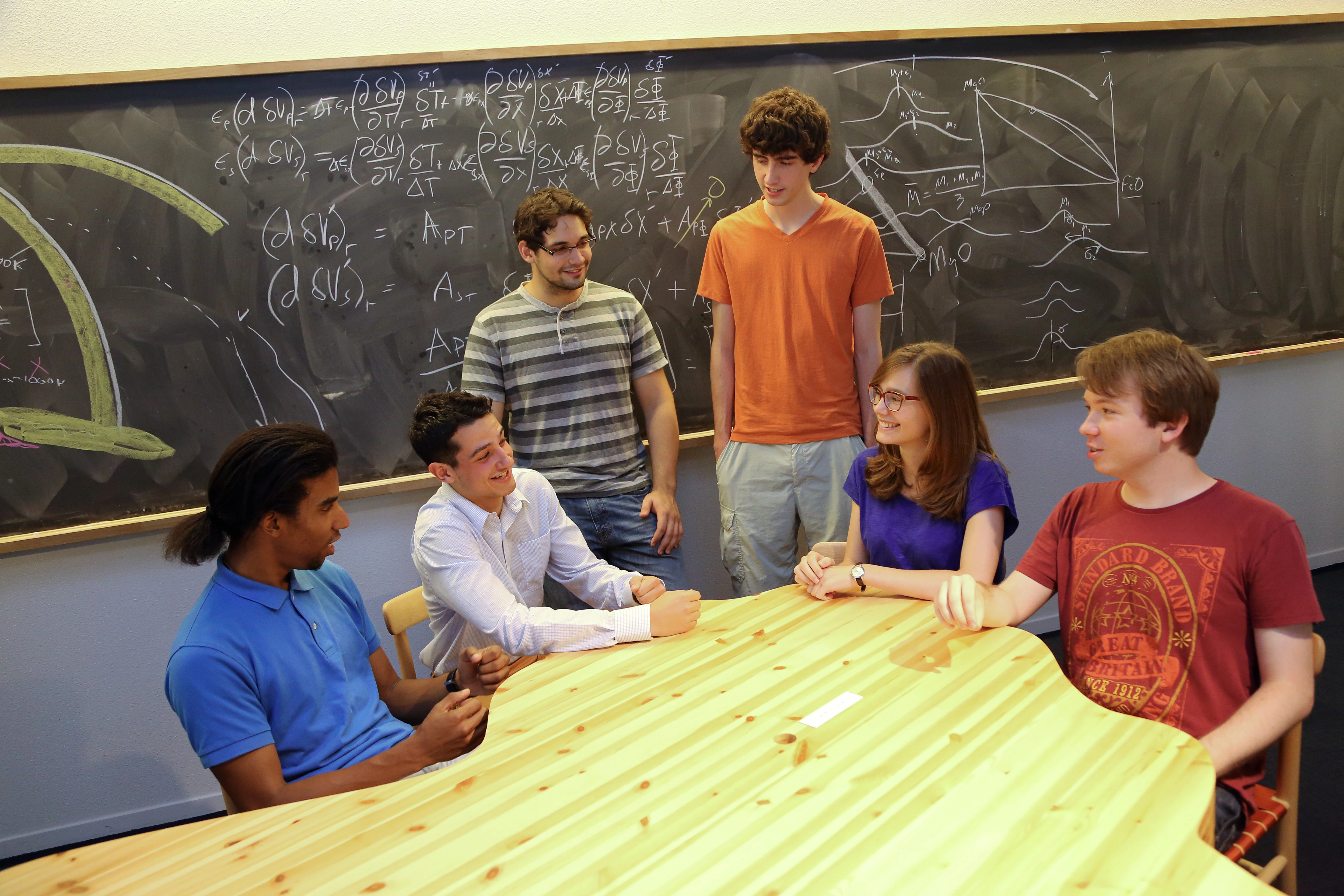どんな研究?
二酸化炭素(CO₂)と聞くと地球温暖化の諸悪の根源というイメージを連想するかもしれません。しかし、二酸化炭素の中にある酸素や炭素は、われわれにとって必要不可欠な元素であり、CO₂は有用な酸素や炭素の原料とも言えます。
産業革命以来、化石燃料の使用は増加の一途をたどり、人間の活動で排出される二酸化炭素は膨大に増え続けてきました。そこで、二酸化炭素を資源化する一環で注目されてきたのが接触変換という技術です。接触変換は、二酸化炭素を水素と反応させ、燃料や化学原料として使えるメタノールに変える技術です。この技術は、1970年代に始まり、その後2010年代前半頃から様々な触媒を利用して変換効率を高める方法の開発が進みました。

触媒とは、自分自身は変わらずに、化学反応を早く進めたり、効率よく進めたりしてくれる「助っ人」ですが、接触変換においては、利用する触媒によって生成されるメタノールの量に差があり、その差が生まれるのは何故なのか、詳しい仕組みはわかっていませんでした。
東京科学大学の細野秀雄(ほその・ひでお)特命教授らの研究チームは、自分たちが2004年に発表し、現在では液晶や有機ELディスプレイの画素の駆動回路などに広く使われているインジウム・ガリウム・亜鉛酸化物(a-IGZO:アモルファス・イグゾー)という材料に注目し、a-IGZOが二酸化炭素からメタノールを作る優秀な触媒になることを世界で初めて発見しました。
ここが重要
ここで用いたのは粉末状のa-IGZOです。その特徴は、表面積がとても大きく、たくさんの電子を持っていることです。そのため、水素を炭素と酸素のいずれとも結合させることができます。調べてみると、a-IGZOに含まれるインジウムなどの酸化物は、それに含まれる電子が水素ととても相性が良く、プラスの水素原子とマイナスの水素原子の両方を作りやすいことがわかりました。それこそが、二酸化炭素を効率よくメタノールに変えるためのカギだったのです。
さらに、少しだけパラジウム(Pd)という金属の触媒を加えると反応がぐんと速くなり、しかも、できたもののほとんどがメタノールでした。Pdはメタノールに変える反応の場所になるわけではなく、水素分子を二つの水素原子に分けて酸化物へ送り込むことで、触媒としてのa-IGZO本来の力を最大限に引き出してくれたのです。
今後の展望
この技術は、二酸化炭素を役に立つ原料として使うための重要なカギになります。材料や仕組みを工夫することで、これまでよりも少ないエネルギーで、しかも、環境にやさしい方法で化学反応を進められるようになるかもしれません。
将来は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーで作った水素と組み合わせることで、石油に頼らずに燃料や化学製品を作ることができるようになり、地球にやさしい社会づくりに貢献できると期待されます。
研究者のひとこと
ディスプレイ材料として開発したa-IGZOが、CO₂変換でここまで活躍するとは思っていませんでした。わたしたちにとって、電子や水素の振る舞いは非常に興味深い研究対象です。半導体と触媒は全く異なる研究分野になっていますが、考え方には相互に通用するものが少なくありません。これらを深く理解すれば、新しい触媒の可能性がまだまだ広がると思っています。
(細野秀雄:東京科学大学 総合研究院 元素戦略MDX研究センター 特命教授 / 東京科学大学 栄誉教授)

この研究をもっと詳しく知るには
お問い合わせ先
研究支援窓口