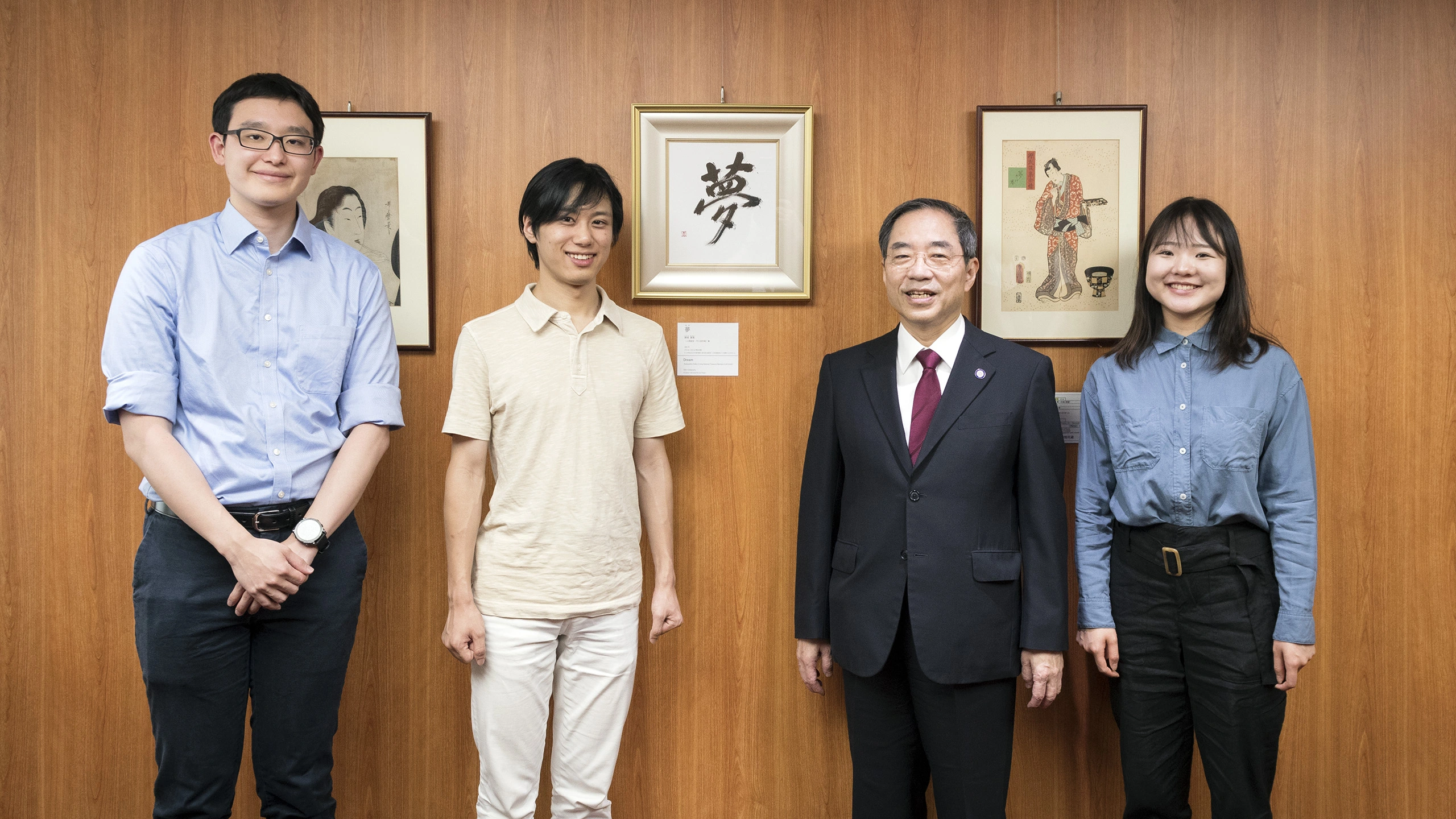
iBScプログラムは、2024年度に開始された、医学科の学生が9カ月間インペリアル・カレッジ・ロンドン(以下「インペリアル」)に渡航し理学士(Bachelor of Science)の学位取得を目指すことができる学生派遣プログラムです。
インペリアルと本学との間の学生交流は、博士後期課程学生交流プログラム(Imperial-Science Tokyo Global Fellows Programme)を始め、医学科生などを通じて活発に実施されています。医学科生の交流は2004年に始まり、これまで約20年に渡って学生交流プログラムを継続してきました。インペリアルからは、毎年4~5名の学生を約3カ月間の研究実習にて受け入れる一方、本学からは、2023年度まで、医学科4年次のプロジェクトセメスター(約5カ月間の研究実習)の一環として、毎年4~5名の学生をインペリアルに派遣してきました。この交流プログラムは両大学の学生にとって非常に人気の高い留学機会となっており、これまで計160名を超える交流学生がこのプログラムに参加しています。
この度、本学の学生に提供してきた5カ月の研究留学の枠を超えて、体系的なサイエンスの素養を学ぶ機会の創出および高度専門的医療人の養成を目指し、インペリアルとの綿密な協議を重ね、東京科学大学はインペリアルが提供する「iBScプログラム」に英国・アイルランド外の大学で初めての参加校として認められ、2024年度からプログラムへの学生派遣を開始しました。
本学及びインペリアルでの派遣学生選考を経て、2024年9月より派遣がスタートした第一期生3名(医学科4年生2名、MD-PhDコース生1名)が、9カ月間のプログラムを修了し無事に帰国しましたので、プログラムでの経験を共有して頂きました。
医学科4年 樋上 真梨(参加コース:グローバルヘルス)
このプログラムについて初めて聞いた時、私はすぐに興味を持ちました。というのも、大学から経済的・事務的な支援を受けながら、世界有数の大学で学位取得を目指せるこの機会は、絶対に見逃せないと思ったからです。インペリアルは英国で最も卓越した研究成果と環境を誇る大学であり、特に、グローバルヘルス分野の研究において、英国は日本よりも格段に進んでいて、日本では得ることができない知識や経験を学べると思い、応募を決意しました。
応募を決めるまでは早かったものの、語学試験の必要スコアを達成するのは簡単ではありませんでした。実際、学内応募の締切時点ではインペリアルが求める必要スコアに少し足りない状態での応募となりましたが、その後、本学のスタッフや先輩学生からアドバイスをもらいながら、渡航前には無事達成することができました。
また、英国渡航前に2ヶ月程、本学が提供するPre-sessionalコース(事前学習)に参加しましたが、それだけでも応募の価値があると思うほどの内容でした。マンツーマンでレポートの書き方やプレゼンテーションの指導が受けられ、レポート作成やプレゼンテーションの機会が多いiBScでは、事前学習で得たスキルが大いに役立ちました。取り扱うテーマも自分で選択できるので、iBScで学ぶ内容への理解を事前に深める機会としても活用することができました。
ついに9月の渡航を迎えました。日本を長期で離れるのが初めてだったため、現地の生活に不安もありましたが、実際にはヨーロッパの多様性のある環境は居心地良く感じられ、自分が周りと違うと意識する必要もなく、みんなが歓迎してくれていると感じられました。また、ロンドンは東京同様大きな都市なので、折に触れて東京の暮らしと似ている部分も感じられ、9カ月間安心して生活することができました。

医学科4年 兼松 快(参加コース:神経科学・メンタルヘルス)
インペリアルで学び始めてすぐに気づいたのは、学習環境が日本で慣れ親しんだものとは大きく異なる、ということでした。インペリアルでは、議論・批判的思考・自主的な学習に重点が置かれていました。その環境で私は、より積極的に課題と向き合い、問題解決のための異なる視点やアプローチを検討するようになり、大きな成長が得られたと感じています。また、時間が経つにつれ、このアプローチが「単なる知識の暗記」だけでなく、「医学の理解をより深める」ことに役立っていることを実感するようになりました。
こういった環境の違いの中で、教科書や既成のラボマニュアルに従うのではなく、自ら原著論文を検索して読んだり、独自に考え科学的な議論にも積極的に参加したりすることが求められました。最初は気圧されることもありましたが、定期的に行われるマンツーマンの指導、フィードバックセッション、学生同士が協力して取り組む体制が、私の成長を後押ししてくれました。その過程で、知識を暗記するだけではなく、「知識を創造するスキル」が鍛えられたと感じています。
授業以外では、寮生活もまた貴重な経験でした。世界中から集まった学生たちとキッチンを共有し、一緒に料理をしたり、夜遅くまで話しこんだりすることもありました。サイエンスだけでなく、異なる文化、信仰、価値観についても深く知ることができました。
もちろん、楽しいことばかりではなく、特に英語で膨大なレポートを書いたり、異なる文化や環境に慣れたりするまでには苦労したのですが、これらの挑戦も自分自身の可能性を拡げ、予想外の学びを得る機会にもなりました。

MD-PhDコース 博士課程3年 原 雄一郎(参加コース:免疫・感染症)
iBScプログラムの最後の数週間は、プログラムの中でも最も過酷な期間でした。iBScプログラムはModule1~3の3段階に分かれていて、Module1と2で研究に必要なスキルを徐々に身につけてきた学生達にとって、Module 3はまさに1年間の集大成となります。
Module 3は、本学の医学科のプロジェクトセメスター(プロセメ)と似ていて、各学生が研究プロジェクトに配属され、指導教員のもと研究を進め、最終報告書とプレゼンテーションに取り組みます。私にとって、すべて英語で行うという点を差し引いても、この課題はプロセメよりもはるかに難易度が高く感じられました。それは、iBScの方がより集中的なカリキュラム構成となっており、限られた時間内で多くの内容をスピーディーにこなす必要があったためです。そんな中、学生が自分の強みと課題を十分に理解し、成長・改善することができるよう、丁寧に時間をかけてフィードバックを提供してくれた先生方には心より感謝しています。
本学とは異なる学びの環境に身を置いたことで、物事を多角的に捉える力が養われ、自身の大きな成長につながったと感じています。「異なる研究文化を理解し、多様な視点を取り入れ、柔軟に問題に取り組む」というアプローチを実践的に学べたことは、何にも代え難い経験になりました。今後、研究や医療の分野でのキャリアを築いていく中で、複雑な症例の診断や研究デザインの立案といった場面でぜひ活かしていきたいと考えています。
このプログラムは、単に科学的知識を深めるだけでなく、さまざまな場面で必要とされる適応力や包括的な思考力を養う機会を提供してくれました。将来、医療分野において価値ある貢献をしていくための確かな土台となる経験を得られたと、確信しています。
