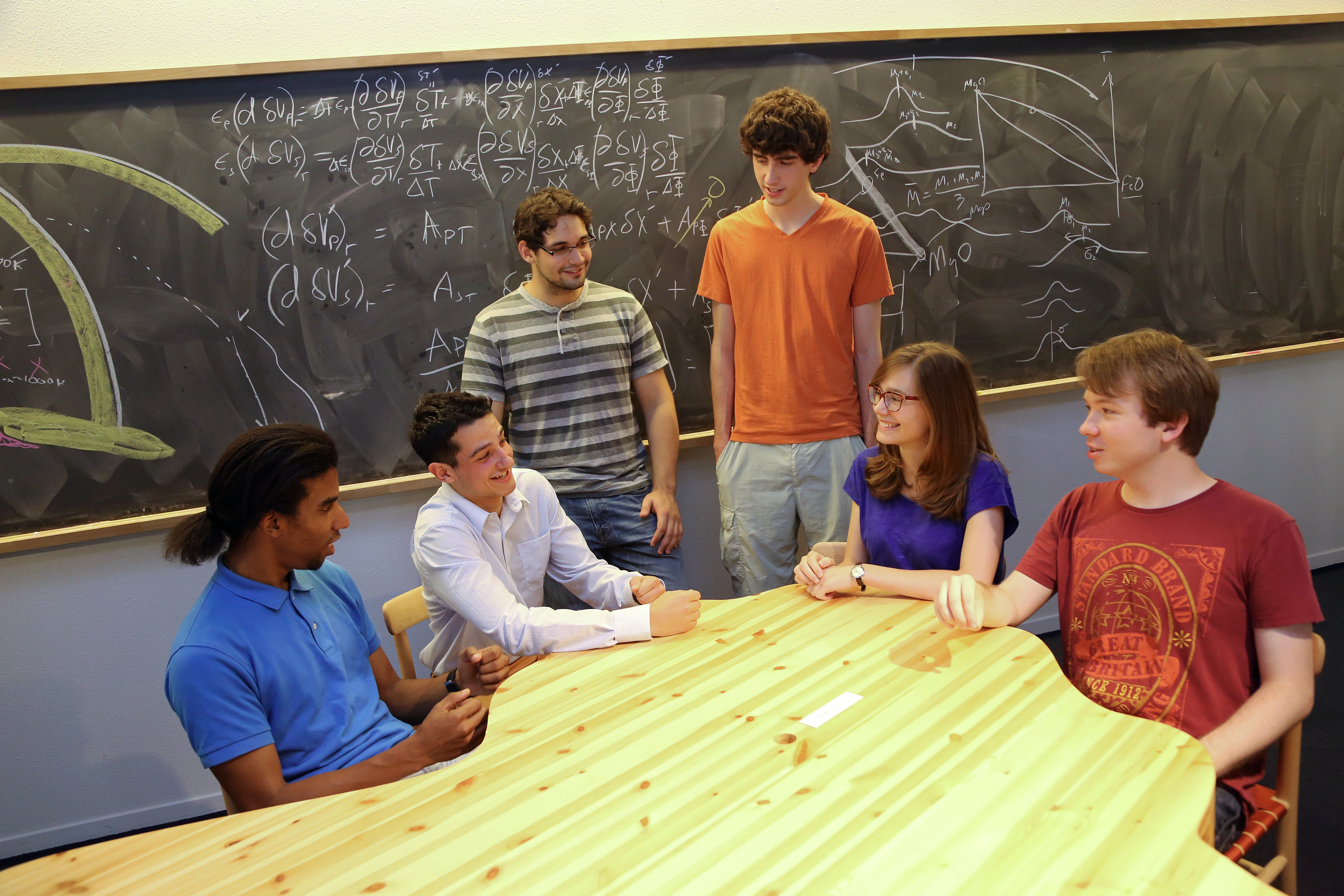どんな研究?
急性呼吸促迫症候群(ARDS)は、重い肺炎や敗血症などでみられる、命に関わる病気です。COVID-19パンデミックの際は、多くの人が肺炎の重症化でARDSに苦しみ命を落としましたが、いまだに有効な治療薬はありません。
これまでの研究で、ARDSの原因には「好中球」という免疫細胞が関係し、炎症を悪化させることがわかっていました。一方で、「IL-4」というタンパク質がARDSの炎症をおさえることも知られていました。
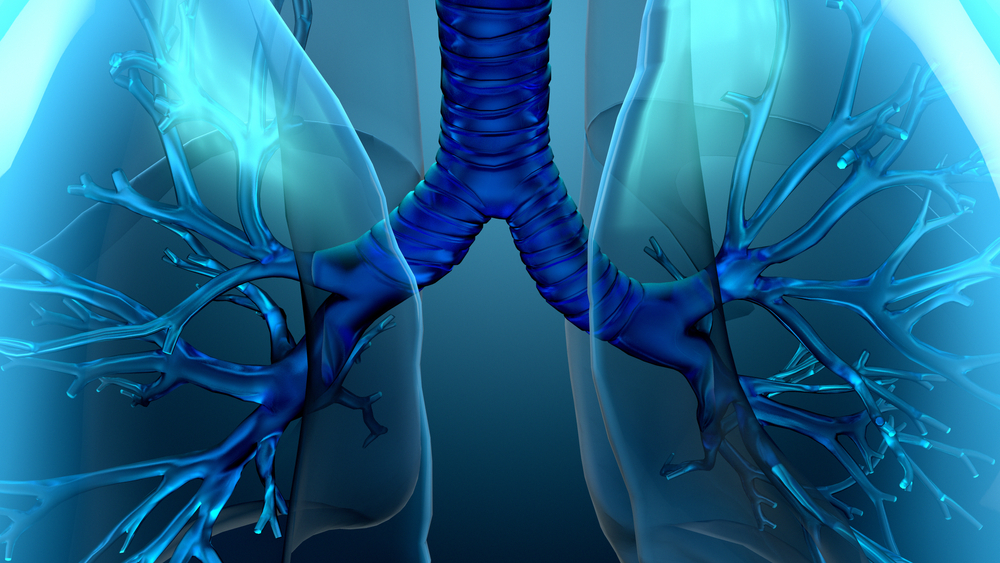
つまり、IL-4の働きをうまく活かせば、ARDSの新しい治療法につながる可能性があります。しかし、そのIL-4が実際にどの細胞で作られているのか、そしてどうやってARDSの炎症をしずめるのかは長い間わかっていませんでした。
ここが重要
東京科学大学(Science Tokyo)の三宅健介(みやけ・けんすけ)准教授を中心とする研究チームは、その謎を解明しました。カギを握っていたのは「好塩基球」という免疫細胞です。好塩基球は、血液中の免疫細胞全体のわずか0.5%しかなく非常に少ないのですが、炎症がピークを過ぎて回復に向かう時期に大活躍していることがわかりました。
研究チームはマウスを使った実験で、好塩基球を取り除くと炎症が長引き、肺がうまく回復できなくなることを発見しました。さらに、炎症が落ち着き始める時期には、肺に好塩基球が入り込み、IL-4を分泌することがわかりました。
そして、このIL-4が好中球に働きかけることで、炎症を引き起こす物質(炎症性サイトカイン)の量が抑えられ、好中球の活動を落ち着かせ、肺の炎症の回復を助けているという仕組みが明らかになりました。
今後の展望
この成果は、これまで治療法がなかったARDSを治療可能な病気に変えるかも知れません。特に敗血症やCOVID-19のように重症の呼吸不全を起こす患者さんでは、血液中の好塩基球が少ないほど予後が悪い、という研究報告もあります。今回明らかになった「好塩基球―IL-4―好中球」の仕組みをうまく利用した新しい薬や治療法の開発が期待されます。
研究者のひとこと
好塩基球は血液中でも数が非常に少なく、これまであまり注目されてこなかった細胞です。近年の研究では、少数ながらアレルギーを引き起こす「悪玉細胞」としての役割が注目されてきました。
しかし今回、呼吸器内科の先生方と私たち免疫学の研究者がチームを組んで研究を進めた結果、好塩基球がARDSにおいては「善玉細胞」として働き、肺の炎症をしずめる主役となるという予想外の結果を明らかにしました。
今後もこのチームで研究を深めることで、ARDSで苦しむ患者さんを救う新たな治療法の開発につながることを心から願っています。
(三宅健介:東京科学大学 総合研究院 准教授)

この研究をもっと詳しく知るには
お問い合わせ先
研究支援窓口