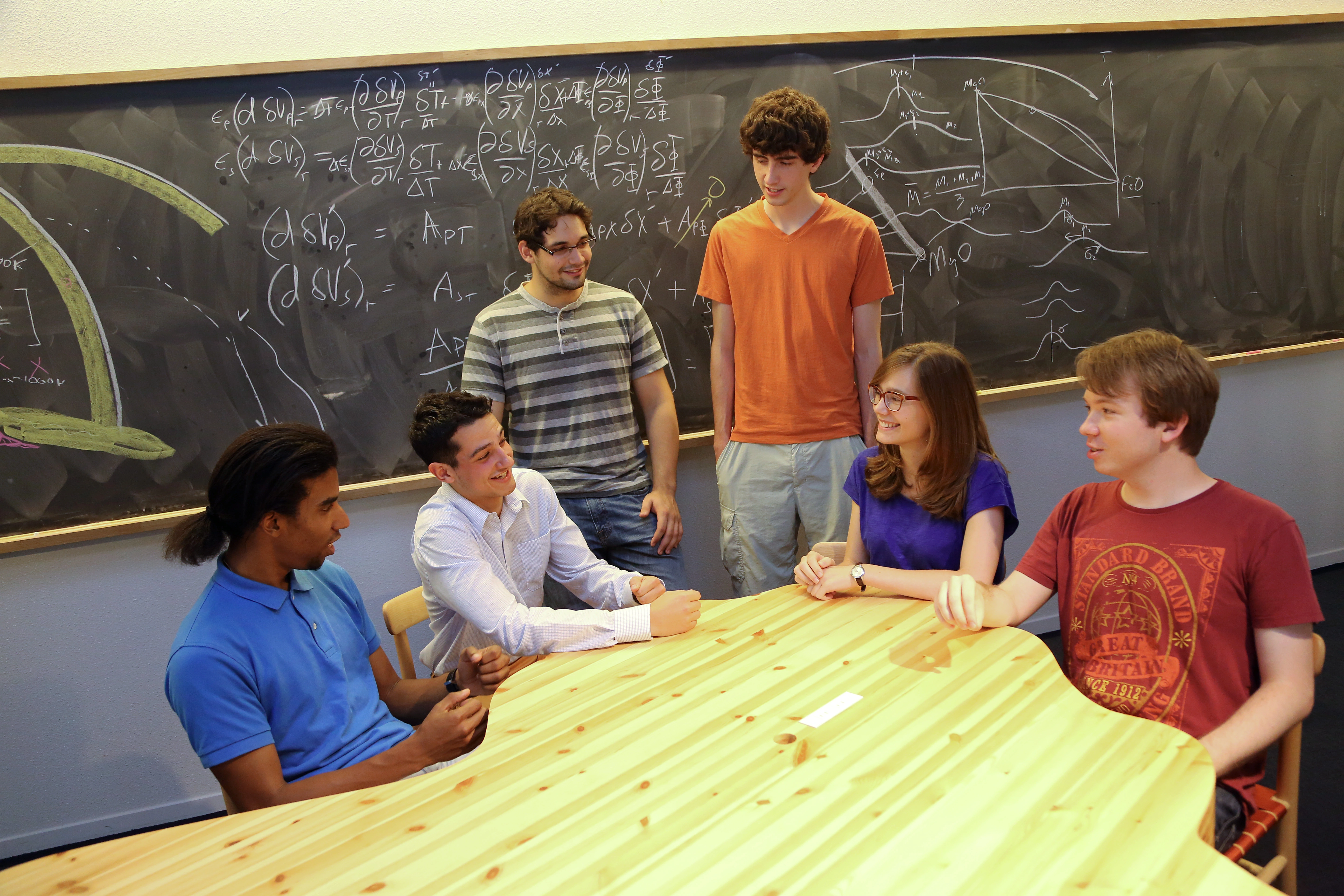どんな研究?
歯を支える骨(歯槽骨・しそうこつ)は、病気やケガによって壊れてしまうことがあります。病気が治ることで自然に骨がつくられ、再生していきますが、治りきらなかったり、欠けたままになってしまうことがあります。
そうした時に、効率的に骨の再生を促す方法の確立が望まれてきました。そこで近年注目されているのが、歯の内側にある柔らかい組織(歯髄)に存在する歯髄幹細胞(しずいかんさいぼう、hDPSCs)という細胞です。

hDPSCsは、様々な細胞や組織に成長(分化)することが知られていますが、特に骨や歯の材料になるような硬い組織に分化しやすいことが知られています。東京科学大学(Science Tokyo)の川島伸之(かわしま・のぶゆき)准教授らの研究チームは、マイクロ RNA(miRNA)-27a という小さな RNA 分子が、hDPSCs に「骨を作れ!」という指令を出す働きをしていることを突き止めました。
ここが重要
一般に、マイクロ RNA は、様々な遺伝子の働きをコントロールする「オペレーター」のような存在として知られています。川島准教授らの研究では、miRNA-27a は、骨づくりを邪魔するタンパク質の機能をストップさせることで、骨づくりを助けることが分かりました。
邪魔なたんぱく質が無効化されると、「骨を作れ」というメッセージを伝えるタンパク質と、骨を育てるタンパク質が活発に働くようになったのです。実験では、miRNA-27a を多く持たせた hDPSCs をマウスの頭の骨に移植しました。すると、実際に新しい骨ができる様子が確認されました。つまり、miRNA-27a が hDPSCs の骨づくりパワーを高めてくれるということです。さらに、miRNA-27aには、細胞や体の組織が傷つく原因となる炎症を抑える働きもあります。
今後の展望
この成果は、歯や顔の骨を再生させる再生医療の分野に大きなインパクトを与えます。たとえば、骨が失われた場合でも、患者自身の幹細胞と miRNA-27a を使って修復できる未来が近づいています。将来は、注射一本で骨が再生するような治療も夢ではないかもしれません。
また、マイクロ RNA は次世代の薬として注目されており、今回の成果はその可能性を広げるものです。
研究者のひとこと
今回得られた結果は、骨や象牙質といった硬組織の誘導を目指すさまざまな事象に応用できる可能性があると考えています。今回は歯髄幹細胞を移植することで骨再生を試みましたが、今後、幹細胞の移植を必要とせずに再生が可能となれば、より簡便で実用的な手法となるでしょう。そのような未来の実現を期待しています。
(川島伸之:東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 歯髄生物学分野 准教授)

この研究をもっと詳しく知るには
お問い合わせ先
研究支援窓口