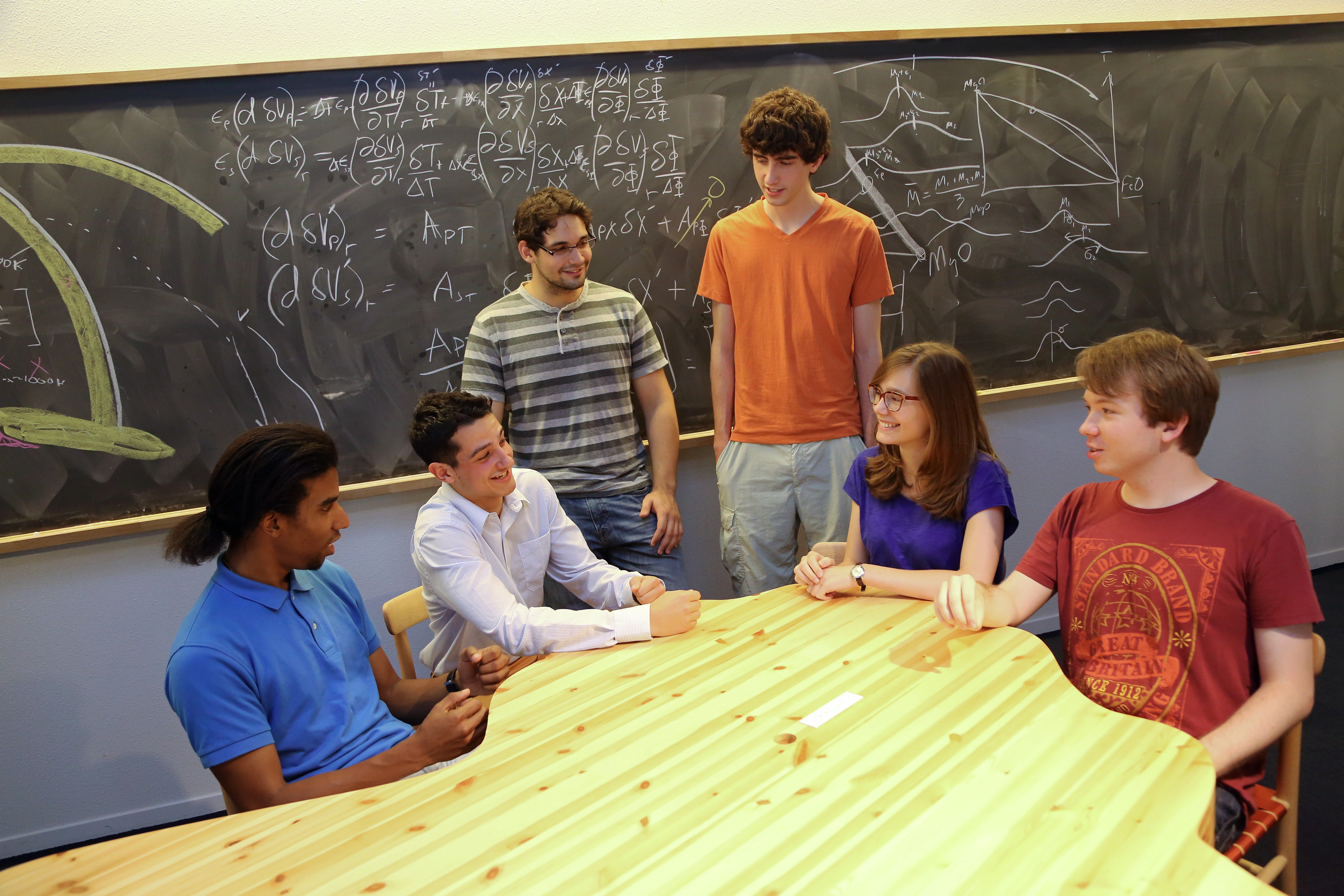どんな研究?
現代の暮らしには、電気はなくてはならないものです。でも、火力発電などで石油や石炭を燃やして電気をつくると、大量の二酸化炭素(CO₂)が排出され、地球環境に影響を与えます。そこで今、CO₂をほとんど出さず、環境への負担が少ない「クリーンエネルギー」が大きく注目されています。
そのひとつが「燃料電池」です。これは、水素と空気中の酸素を使って電気を生み出すしくみです。火を使わずに化学反応で電気をつくり、CO₂を出さず水だけが排出されるというとてもクリーンな発電方法です。

燃料電池の中では、水素と酸素の原子がイオンとなって材料の中を移動し、水を生成しながら電気を生みだします。特に、水(H₂O)の元になる酸化物イオン(O²⁻)やプロトン(H⁺)といったイオンが、どれだけスムーズに動けるかが発電の効率を決める大きなカギになります。イオンが材料の中をうまく移動することによって、発電効率が向上するのです。
そこで注目される新しい電池材料のひとつが「Ba₇Nb₄MoO₂₀」というバリウムやニオブ、モリブデンを含むセラミック材料です。この材料は、乾いた状態でも水を含んだ状態でも、イオンが材料の中をスムーズに移動できるという特徴があります。こうした性質をもつものは「イオン伝導体」と呼ばれています。しかし、「水があるとどうなるのか?」「酸化物イオンやプロトンはどう動いているのか?」といった基本的な仕組みはまだわかっていませんでした。
ここが重要
東京科学大学(Science Tokyo)の八島正知(やしま・まさとも)教授らの研究チームは、Ba₇Nb₄MoO₂₀に水分があると、酸化物イオンの動きがさらに活発になることを初めて実証しました。500℃の条件で、乾燥時よりも水蒸気を含むほうが約2倍も速くイオンが動けることが分かったのです。
さらに驚きだったのは、これまで「水があると主にプロトンが動く」と考えられていたのに、実際には湿った状態でも、電気の流れは、ほとんどが酸化物イオンの移動によることが明らかになったことです。
さらに研究チームは、精密な測定やコンピューターシミュレーションにより、材料の中に「余分な酸素」が入り込み、それがイオンを動き易くしていることも突き止めました。このメカニズムが酸化物イオンのスムーズな移動を支えていたのです。
今後の展望
八島教授らの研究成果は、燃料電池の未来に新しい光をもたらします。優れた材料の特性を理解して利用すれば、燃料電池のコストを下げ、日常生活での利用を広げるカギになります。
また、今回のように酸化物イオンとプロトンの両方が動けるイオン伝導体を活用すれば、燃料電池をより高性能にできますし、それを動かすために必要な装置をシンプルにできると期待されています。こうした技術は、地球にやさしいエネルギー社会の実現に向けた大きな一歩になると期待されています。
研究者のひとこと
これまでは、水があるとイオン伝導度が増大する理由はプロトン伝導という「常識」がありました。でも今回の実験では、逆に水があることで酸化物イオンがよりスムーズに動けるようになることがわかりました。これは従来の考え方とはちがう意外な発見です。今後も、こうした「常識をくつがえす発見」を重ねて、次世代エネルギーの開発に貢献していきたいと考えています。
(八島正知:東京科学大学 理学院 化学系 教授)

この研究をもっと詳しく知るには
お問い合わせ先
研究支援窓口