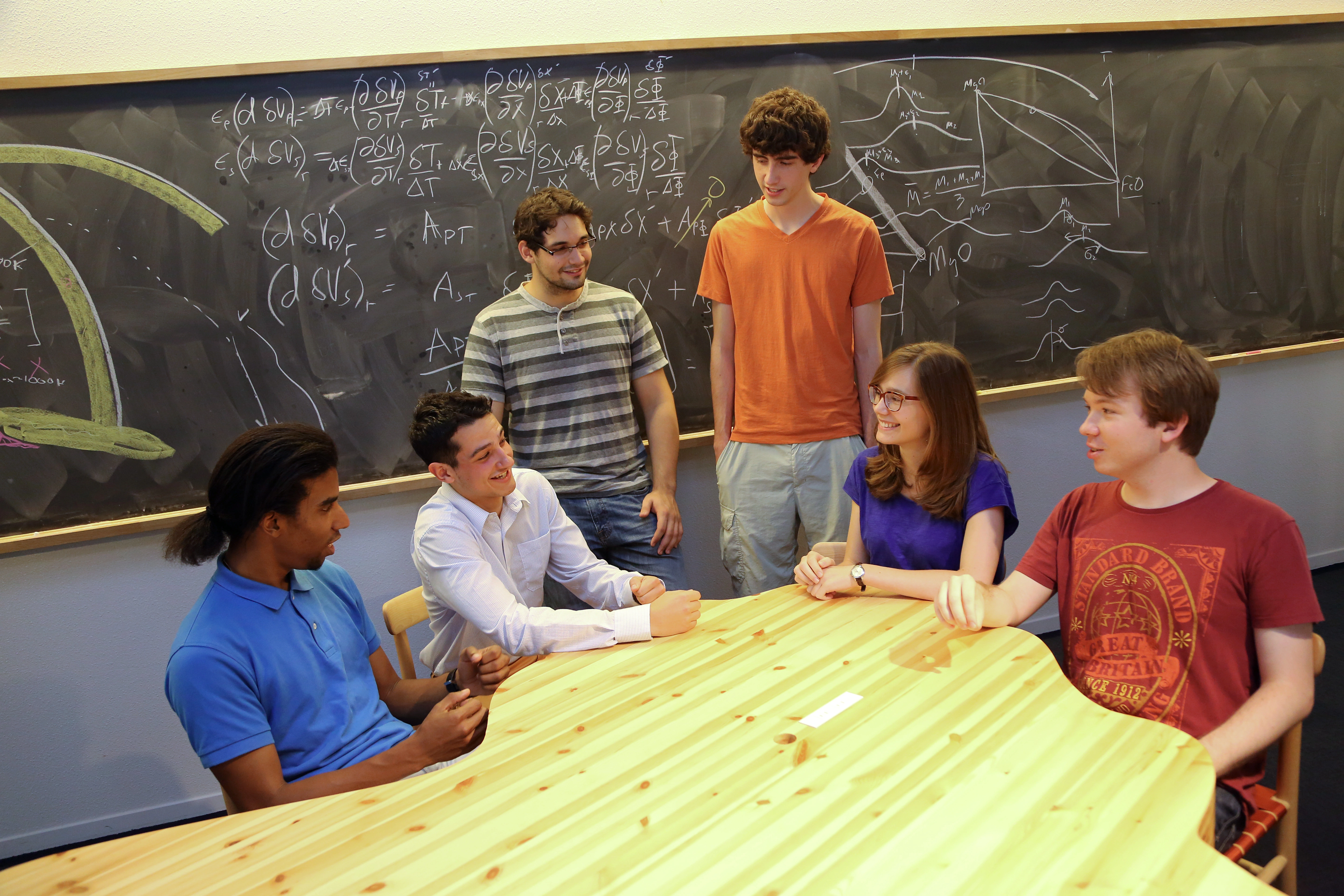どんな研究?
体を病気から守る免疫システムが、誤って自分自身を攻撃することで起こる病気を自己免疫疾患と呼びます。全身性自己免疫疾患(つまり膠原病)の1種である皮膚筋炎では、特徴的な皮膚症状や筋肉の炎症に伴う筋力低下が起こります。皮膚筋炎には様々なタイプがあり、中でも「抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎」の患者さんは、間質性肺炎という肺の病気を併発することが知られています。間質性肺炎は急速に進行することもあり、治療の難しさから命に関わることもあります。
今回、大学院医歯学総合研究科皮膚科学分野の沖山奈緒子教授は、大阪大学、筑波大学と共同でこの病気のメカニズムを解明するために、間質性肺炎を伴う皮膚筋炎に似た症状を示すモデルマウス※用語1を開発しました。

マウスモデルで自己免疫性の間質性肺炎を理解する
ここが重要
これまで抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎を含めた「膠原病の間質性肺炎」モデル動物は開発されていなかったため、世界初の事例となります。研究チームはこのマウスを用いて、体内で炎症を引き起こす働きを持っているインターロイキン-6(IL-6)※用語2という物質が、間質性肺炎の進行とともに肺が線維化することに深く関係していることを発見しました。
今後の展望
このモデルマウスが新たに開発されたことにより、抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎に対して、より疾患特異的な治療法が開発されることが期待されます。
研究者のひとこと
抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎の患者さんを代表に、膠原病の患者さんの多くで、間質性肺炎が命を脅かします。モデルマウスの開発は、病気の病態解明だけではなく、免疫機構の基礎的理解から新しい治療法の開発にもつながる大きな一歩です。

用語説明
※ 用語1. モデルマウス:対象の病気と同じような症状を示すように、薬剤投与や遺伝子改良をした実験マウス。
※ 用語2. インターロイキン-6:感染防御における免疫系の反応を引き起こすのに役立つ分子。一方で、インターロイキン-6の濃度が高いと、特に自己免疫疾患において、腫れや炎症、組織の損傷を引き起こす可能性がある。
この研究をもっと詳しく知るには
お問い合わせ先
研究支援窓口
- 備考
- お問い合わせは https://www.rdc.isct.ac.jp/contact/ からご連絡ください。