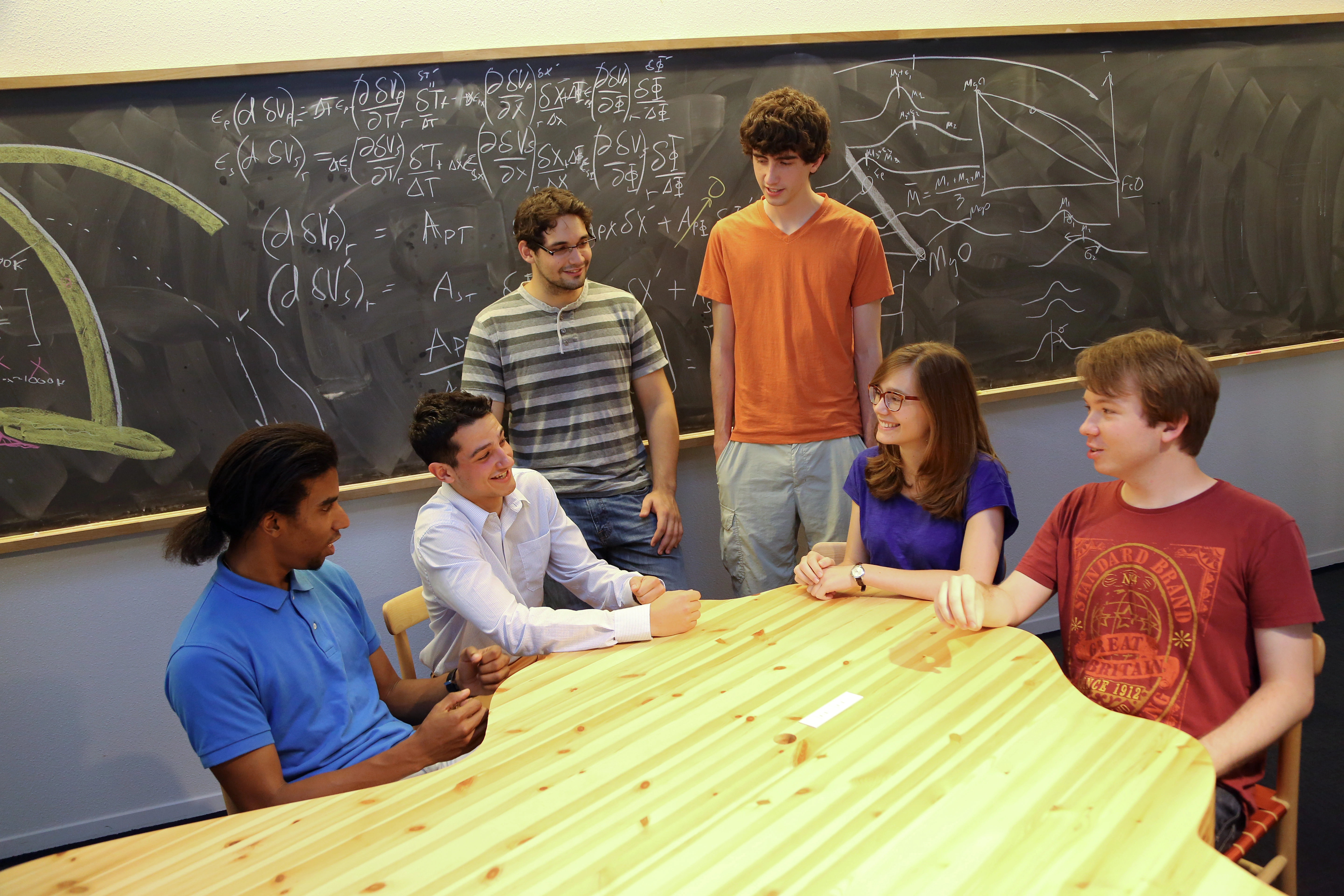どんな研究?
魚の繁殖方法は驚くほど多様です。卵を水にばらまくだけの種類もいれば、口の中で育てたり、泡の巣を作ったり、おなかの中にある袋で育てたりと、様々な「子育てスタイル」があります。こうした卵を守るタイプの魚たちは、進化の中で幾度となく登場してきました。
しかし不思議なことに、魚が卵を守るタイプにいったん進化すると、その後、卵を守らないタイプへ逆進化した例、つまり元のタイプに戻った例は、ほとんど見つかっていません。なぜ戻れないのでしょうか?

ここが重要
東京科学大学(Science Tokyo)の長澤竜樹(ながさわ・たつき)助教らの研究チームは、240種の魚のゲノムを調べました。そして、ある重要なことを発見しました。卵を守るタイプの魚の間では、共通して、卵の外側を守るかたい膜(卵膜)をつくる遺伝子が壊れていて、機能しなくなっていたのです。
一度「卵を守る戦略」に進化すると、卵膜をかたくする遺伝子が不要になり、やがて壊れていく、そして、その遺伝子が壊れてしまうと「卵を守らないスタイル」にはもう戻れない、そういう事が起こったのだと考えられるのです。
つまり、魚の子育てスタイルの進化は、遺伝子の変化を伴う一方向にしか進めない「片道切符」だったと言えます。
今後の展望
この発見によって、まだ詳しく観察されていない魚の繁殖スタイルを、ゲノムから「卵を守るタイプかどうか」が推測できるようになります。たとえば、深海にすむ魚や絶滅が危惧種の魚などでも、体の一部からDNAを調べれば、繁殖のスタイルを推測できるかもしれません。
また、ゲノムの情報変化を伴う一方向進化は、魚だけでなく、哺乳類(たとえば人間)の進化にも関係している可能性があります。すると、人間の進化の理解にもつながるかもしれません。
研究者のひとこと
魚のさまざまな繁殖スタイルの裏に、 “見えない進化の痕跡”が共通してあることに驚きました。子育てという行動が、遺伝子のレベルで記録されており、さらに、それが後戻りできない進化と知って、進化の不思議さに改めて興味がわいてきました。当分、研究はやめられそうにありません。(長澤竜樹:東京科学大学 生命理工学院 助教)

この研究をもっと詳しく知るには
お問い合わせ先
研究支援窓口