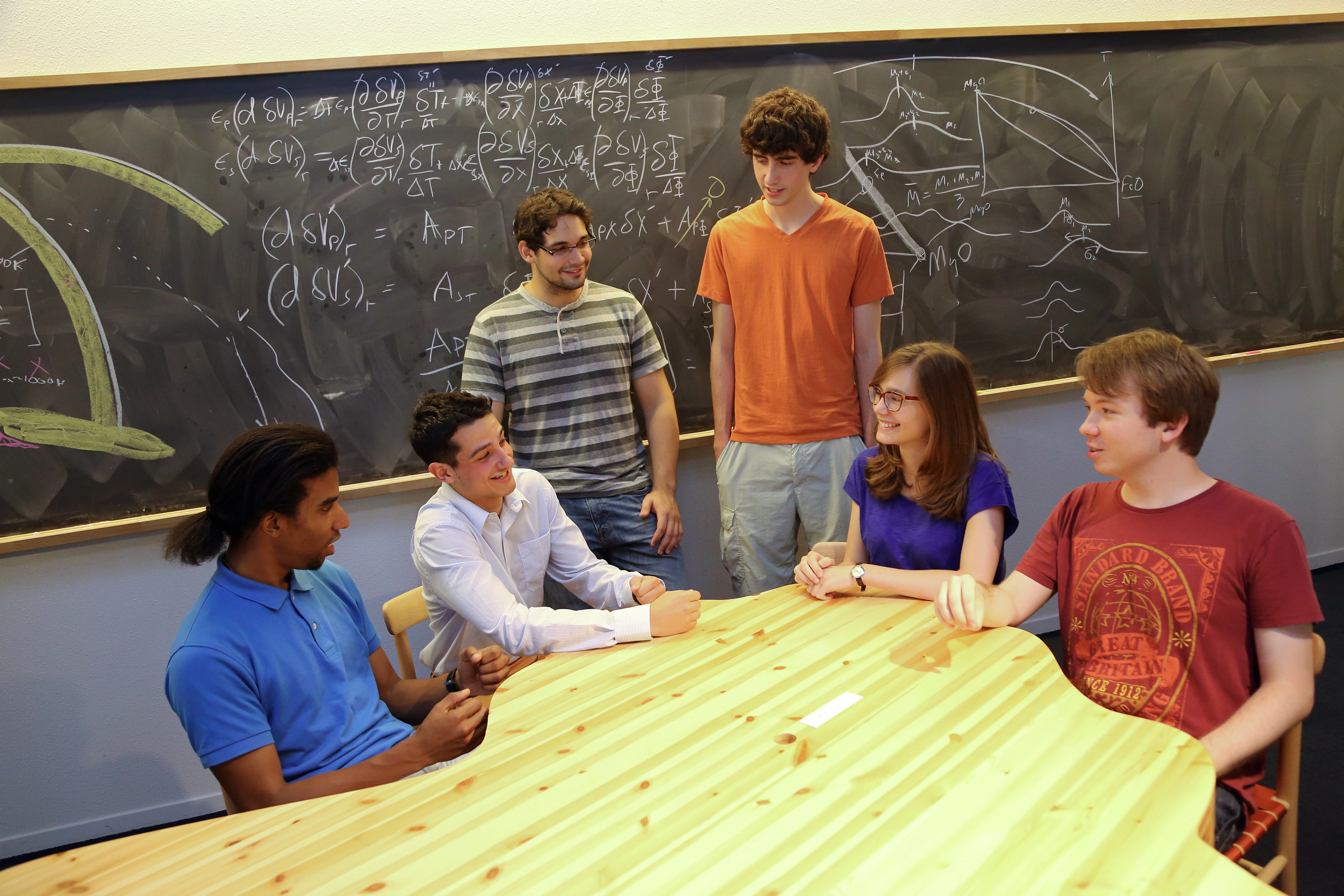どんな研究?
動物の体は、神経や筋肉、骨など、さまざまな種類の組織が組み合わさってできています。こうした組織は、体をつくる過程でも互いに歩調をそろえながら形を変えていきます。
たとえば背骨や手足のように、体の「軸」となる部分では、周囲にある複数の組織が成長のペースをそろえないと、軸全体がゆがんだり、うまく機能しなくなってしまいます。しかし、異なる組織どうしがどうやって成長のペースをそろえているのか、そのしくみはよく分かっていませんでした。

ここが重要
東京科学大学(Science Tokyo)の河西通(かわにし・とおる)助教らの研究チームは、ゼブラフィッシュの体の中心を走る軸、すなわち将来背骨ができる位置にあたる部分で、3つの異なる組織―脊索(せきさく)・底板(ていばん)・下索(かさく)―が、どのように足並みをそろえて伸びていくのかを調べました。
このうち脊索は、体の基本的な形がつくられはじめる初期の段階に現れる組織で、背骨や筋肉などの発生を促す重要な役割を果たします。また、背骨ができるまでは体の中心で棒状に固くなり、「仮の背骨」として働きます。脊索の成長は、新しい細胞が尾の後ろに次々と追加されていくことで進みます。例えるなら、お店の開店を待つ行列に人が次々に加わって列が長くなっていくようなイメージです。
一方、底板と下索は、すでにある細胞が後ろに向かって移動することで伸びるという、まったく別のしくみを使っていました。新しい細胞が追加されるのではなく、並んでいる細胞たちが列を維持しながら移動していくのです。まるで、お店の入り口が少しずつ後ろに動き、それに合わせて並んでいた人たちも順番を保ちながらみんなで少しずつ後ろへ下がっていくようなイメージです。
底板や下索の細胞の移動には、「FGFシグナル」とよばれる化学物質が関わっていました。さらに、移動中の細胞は隣り合う細胞どうしがつながっているため、互いに引っぱり合うような力が生じます。
引っぱられた細胞の中では「Yap(ヤップ)」というタンパク質が働きはじめ、細胞の増殖を促すスイッチが入ることがわかりました。つまり、移動と増殖がうまく組み合わさることで、列が途中で途切れることなく、底板と下索も脊索と同じスピードで伸びることができるのです。
研究チームはこうした観察結果をもとに、脊索を「リーダー」、底板と下索を「フォロワー」とする数理モデルを作成し、3つの組織が整列した状態を保ちながら伸びていく様子を再現しました。このしくみは、実はロボットの群れの動きをコントロールするために使われる「フォーメーション制御※用語1」という工学の考え方とよく似ており、工学理論が生物の体づくりにも当てはまることを示す重要な成果となりました。
今後の展望
フォーメーション制御のしくみは、心臓や手足など他の器官の成長でも使われている可能性があります。今後は、他の器官やゼブラフィッシュ以外の動物においても同様な組織どうしの連携が見られるのかを詳しく調べていく予定です。
また、このしくみに関わる分子の働きを明らかにすることで、動物の体がどのように形づくられるのか、その基本ルールの理解がさらに深まると期待されます。
研究者のひとこと
たくさんの細胞が集まった塊が、たった数日のあいだに、ひとりでに、そして毎回同じように正確に、顔や手足のような複雑な形をつくっていく。その様子を顕微鏡を通して見るたびに、いつも圧倒されます。
今回の研究では、そうした形づくりの背後で、細胞たちが「リーダー」と「フォロワー」に分かれ、まるでチームのように連携して動いていることが明らかになりました。
工学や数学の考え方を生物学に取り入れることで、生き物がどのように体をつくっていくのか、そのしくみの奥深さにこれからも迫っていきたいと思います。
(河西通:東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系 助教)
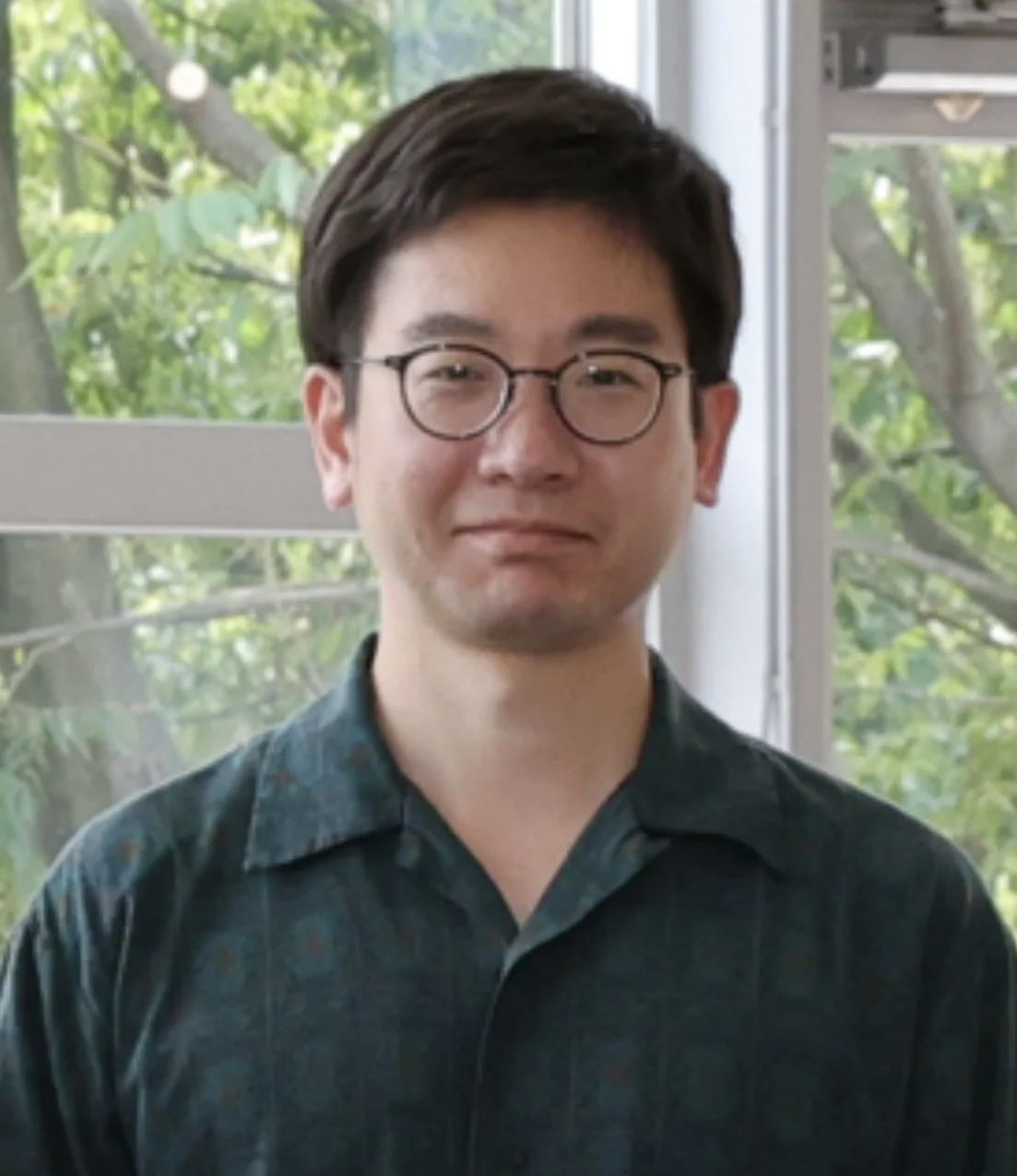
用語説明
※用語1. フォーメーション制御:ドローンやロボットの集団を、整った隊列を保ちながら動かすために考えられた理論です。なかでも、リーダー役の動きに合わせて他の仲間(フォロワー)が一定の距離や位置を保って動くしくみは、フォーメーション制御の代表的な方法のひとつです。
この研究をもっと詳しく知るには
お問い合わせ先
研究支援窓口